
小児がんを患った20代から30代の女性2人が、がん治療前に凍結保存した卵巣組織を体内に移植して出産に成功したことが、聖路加国際病院などの医療チームによって国際学術誌「Climacterics」に発表されました。この成果は2025年12月8日付で掲載され、2026年1月4日に報道されたものです。
今回の2症例は、骨や筋肉などにできる「ユーイング肉腫」という小児がんの患者で、10代から20代の頃に腹腔鏡手術で卵巣の一部を摘出して凍結保存していました。体内に残った卵巣はその後の抗がん剤や放射線治療によって機能を失いましたが、治療が一段落した後に凍結卵巣を腹膜に移植したところ、月経が再開しました。卵巣機能が回復したことで、体外受精を経て2025年に2人とも出産に至りました。
国内では、がん患者が凍結保存した卵巣から出産した例として、卵巣組織を短冊状にして移植する従来の手法での報告が聖マリアンナ医科大学などからありました。しかし、今回聖路加国際病院のチームが用いたのは「サーキュラー・ストリング法」と呼ばれる新しい移植技術です。この方法は、卵巣組織片を糸でつないで数珠状に並べ、腹腔内に作成した腹膜ポケットの中に配置するものです。
数珠状にして移植することで、組織同士の重なりや血流障害を減らすことができ、血流がよくなることで卵巣の機能を長期間維持できると期待されています。従来の短冊状の移植法と比較して、この新しい手法は卵巣組織の生着率を高め、より安定した卵巣機能の回復につながる可能性があります。
聖路加国際病院女性総合診療部の平田哲也部長(生殖内分泌医学)は、「治療と将来の妊娠を両立させる新たな希望となる手法だ。選択肢があることを知ってほしい」とコメントしています。
妊孕性温存治療の選択肢と今後の展望
がんの女性が生殖能力を温存するには、これまでも卵子や受精卵を凍結する手法がありました。しかし、卵巣組織凍結保存は、月経発来前の小児がん患者にとっては唯一の妊孕性温存療法となります。卵巣組織には数千から数万という多数の原始卵胞が含まれているため、短期間で大量の原始卵胞を保存できる点で優れています。
世界的には、2004年にベルギーのドネズ博士がホジキン病患者の卵巣組織凍結・移植による初めての生児獲得を報告して以来、この技術は急速に世界中に広がりました。最新の世界データでは200例以上の児が凍結卵巣組織を移植した後に生まれており、卵巣組織移植あたりの妊娠率は約37%、出生率は約26%と報告されています。
日本国内においても、卵巣組織凍結保存の実施件数は増加傾向にあります。聖マリアンナ医科大学では2010年から卵巣組織凍結の臨床試験を開始し、2019年6月時点で108症例に対して卵巣組織凍結を施行しています。同大学では短冊状に切り分けて移植する手法を用いており、国内で初めてがん患者の卵巣組織凍結・移植による出産例を報告しました。
今回の聖路加国際病院による成果は、数珠状の新しい移植法による出産成功例として、妊孕性温存療法の選択肢をさらに広げるものとなります。小児・AYA世代のがん患者にとって、将来の妊娠の可能性を残すための重要な医療技術として、今後さらなる普及と技術向上が期待されます。







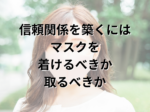

に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)


-300x169.jpg)