- Home
- コラム・インタビュー, 刑務所特集
- 服役中に亡くなった受刑者はどうなる?宮城刑務所分類審議室の職員に聞く

「もし受刑者が服役中に亡くなってしまったらどうなるんだろう?」と気になったことはありませんか?
受刑者は、必ずしも全員が刑期を終えて出所できるとは限りません。健康上の理由で極めて重篤な状態に陥ったり、あるいはそのまま刑務所の中で最期の時を迎えたりすることもあります。
「受刑者が危篤状態になった場合、家族には連絡があるのか?」
「家族が受刑者を看取ることはできるのか?」
「受刑者が亡くなった後はどんな手続きをするのか?」
そんな疑問に答えるべく、受刑者と親族等の関係者をつなぐ役割を担っている、宮城刑務所の分類審議室の職員にお話を伺いました。
<目次>
刑務所の分類審議室(処遇部企画部門(分類))の仕事
刑事収容施設法(正式名称:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)第176条では、受刑者が死亡した場合、刑務所が遺族等に対して死因や死亡日時、遺留物などの存在を通知する義務が定められています。宮城刑務所においてこの通知等手続きを担当しているのが分類審議室(総じて「分類」と称する。)です。特に宮城刑務所は長期刑の受刑者が多く、医療的措置を重視する「医療重点施設」であることもあり、受刑者が重篤な状態になるケースが少なくありません。
受刑者が「重症指定」を受けた場合
分類が遺族等に連絡をするのは、必ずしも受刑者が亡くなったときだけではありません。ケガや病気で命に危険が及ぶ状態になると、刑務所では「重症指定」とされ、この時点で分類から第一報が入ります。連絡は「受刑者本人が希望する相手」「配偶者」「子ども」「両親」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の順に行われ、これらの関係者のうち連絡がとれた者1名を「緊急連絡先」とします。
緊急連絡先の情報は、入所時に受刑者から申告されるのが原則ですが、宮城刑務所では長期刑の受刑者が多いため、10〜20年後に突然連絡を受けて驚かれる方も少なくありません。そのため、分類は連絡時に、今後も緊急連絡先としての連絡が可能かどうかを確認します。また、医師による病状説明や面会の希望有無も同時に確かめます。面会は希望すれば可能ですが、危篤時に一晩付き添ったり看取ることはできません。
受刑者が亡くなった場合
受刑者が亡くなった場合、同法に基づき、緊急連絡先として登録されている遺族等に死亡等を知らせる連絡が入ります。遺体は直接遺族等が持ち帰ることもできますが、実際には、刑務所側が火葬まで手続きを行い、お骨の状態で遺族に引き渡されるのがほとんどです。また、希望すれば人数制限はあるものの、遺族が参列できる葬儀が刑務所内で執り行われます。
しかし、遺族に連絡がつかない場合もあります。受刑者が入所時に緊急連絡先を申告していなかったり、申告された連絡先の方がお亡くなりになっていたり、引っ越したりして所在不明だったりするケースがあるからです。その際は、戸籍照会を行い、照会結果に基づいて電報を送り、相手からの連絡を待ちます。この電報の送付も、前述の緊急連絡先の優先順位に従って行われます。
身寄りがない受刑者はどうする?
身寄りのない受刑者の場合、戸籍照会など可能な限りの手続きを行っても、誰とも連絡が取れないことがあります。そのような場合、火葬後の遺骨は寺院に仮納骨を依頼します。
「公告」について
亡くなった受刑者には、多少の遺留金品が残ることがあります。遺族等の所在が明らかでないため通知ができなかった場合、死亡から6ヶ月後に特定の事項を広く一般に知らせる「公告」と呼ばれる手続きが行われます。刑務所前の掲示板など、一般市民が目にする場所で、亡くなった受刑者の生年月日等や遺留金品に関する情報が掲示されます。この公告を通じて遺族や関係者が情報を知り、遺留金品を受け取るための申請を行うことが可能です。
「国庫帰属」について
公告を行っても遺族や関係者から引取りの申請がなかった場合、遺留金品は「国庫帰属」となります。これは、その金品が国の所有物として扱われることを意味します。通常、亡くなった方の遺品は遺族が整理し引き取るものですが、受刑者の場合、事情はさまざまです。しかし、身寄りがいない場合でも早急に処理されるわけではなく、定められた手順に従い、必要な手続きを進めていきます。
刑務所の分類が抱える課題
受刑者が重症指定を受けた際や死亡時には、緊急連絡先の方々と速やかに連絡が取れることが理想です。特に、昨今の刑務所では一般社会と同様に高齢化が進んでいます。「万が一に備え、緊急連絡先の情報に変更がないか、数年ごとに定期的に確認する対応が今後必要になるかもしれない」と、分類の職員は課題を指摘しています。
刑務所内の霊安室の様子

刑務所のなかで亡くなった方はどのように対応されるかは、前述の分類審議室にうかがった通りですが、仮葬儀の執行については主に教育部で対応しています。

仮葬儀は、亡くなられた方の宗派により、おおむね仏教、キリスト教、神道に分けて行われます。教誨師(きょうかいし)と呼ばれる方が、仮葬儀を行います。
教誨とは、全国の刑務所、拘置所、少年院等の矯正施設において、死刑確定者、受刑者、非行少年等の被収容者からの願い出に対し、
各教宗派の教義に基づき、徳性を涵養し、人間性の回復を図る働きかけを行うことです。
この活動を民間ボランティアとして無償で行っている宗教家が教誨師です。
(出典:全国教誨師連盟)
仮葬儀での音(例えば、お経を唱える声や木魚を叩く音など)は外に聞こえないように配慮されています。音が聞こえることで他の受刑者が死を連想したり、負の念を想起したりすることを防ぐためです。

宮城刑務所では年間約20名がこの霊安室にて仮葬儀を行っているそうです。重篤な方を受け入れる体制を整えていることもあって、仮葬儀が行われる人数は他刑務所よりかなり多いようです。

あくまでも仮葬儀のため、霊安室は十数人が入れる程度の広さでした。仮葬儀を終えると、荼毘に付します。
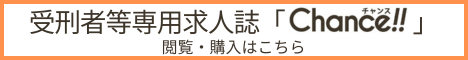
-150x112.png)
-150x112.jpg)
-150x112.png)





に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)
の看板-280x210.jpg)


-300x169.jpg)