- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 独働記#1 副業解禁から7年。“自由に働ける社会”は実現したのか?

「独働記(どくどうき)」は、就職せずフリーランスとして働きはじめ、十数年を経た筆者が、“ひとりで働くこと”の光と影を見つめなおす、連載コラムです。
SNSには映らないリアル、自由の代償、不安と向き合う日々──すいもあまいも噛みしめてきた体験をもとに、現代の「働き方」の本質に迫ります。
~~~~~
2018年1月。政府は働き方改革の一環として、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂。副業禁止の規定を無くし、副業・兼業に関する規定を新たに定めたことで副業は解禁の流れとなった。
そこからコロナ禍を経たことで、私たちは働き方はおろか生き方の再定義を求められることになる。外に出ずとも働く方法を求め、インターネットを通じて在宅で副業・兼業する人も出てきた。
しかし、解禁から7年経ち、未曾有の社会変化を経験した日本社会は、本当に「自由に働く」を実現できているのだろうか。
<目次>
自由に働ける社会? SNSと現実のあいだで揺れる言葉たち
2014年(大学2年次)からフリーランスのコピーライターとして活動する筆者は、インターネット上で仕事の獲得と同業者らとの交流を求めてきた。始めた頃は風当たりも強かったが、社会はより多様な働き方・生き方を求め、先行者である筆者は追い風すら感じるようにもなった。
SNSには“きらびやかな自由”の言葉が並ぶ。「あなたらしく働く」「仕事もプライベートも諦めない」「理想のワークライフバランス」「短時間で高報酬」「副業で悠々自適生活」など。実態にはふれぬ聞こえのいい言葉を使って、業界に手招きする者もいる。
自由には大いなる責任を伴う。仕事は仕事であることに変わりなく、フリーランスであろうと会社員であろうと、そして兼業であろうと、プロとしての確固たるスキルがなければ満足に働くことはできない。至極当たり前のことだ。
新しい働き方に挑戦することを咎める権限など誰にもないが、勇み足につけ込み高額の情報商材を売りつける界隈があることは知っておかなければならない。自分で調べること、自分で決めることを念頭に置き、ミニマムに始めることが副業・フリーランス成功の第一歩だろう。そうでなくてはあまりに厳しい現実と理想の間に身も心も縛られてしまう。ブレークスルーの瞬間を迎えるには、ある程度の期間といくつもの仮説検証を積み上げる必要がある。
副業は解禁された。でも「働き方の選択肢」は本当に広がったのか?
筆者は、フリーランスの実態や必要なスキル・マインドセットに関する登壇を、幾度も経験してきた。そこでは「副業を始めたいが、何から始めればいいかわからない」のほかに、「会社に対する裏切りの感情に似た懸念を抱く」「副業をしなければ生活が苦しいが、上手くいくのか不安」といった相談もいただく。社会の制度というハードは変わろうとも、私たちの行動を縛るソフトは、まだまだアップデートが必要なのかもしれない。
フリーランス駆け出しの頃の筆者は、自由になったつもりが別の制約で理想とはかけ離れたところにいた。肩書も後ろ盾もない不安、クライアントとの不平等な立場、低単価な報酬によって心を削った。それでも生きなくてはならない。社会保険料を、税金を、高騰する一方の生活費を工面しなくてはならない……。
悲観論ばかり話したくはないが、“選択肢がある”ことと、それを“選べる環境がある”ことは全くの別問題だ。フリーランスや副業を始める人は、冒頭で話したきらびやかな自由を求める人ばかりではなく、本業の収入のみでは満足に生活できなかったり、自身の健康や家庭の事情から、やむを得ず会社員以外の働き方を強いられたりするケースもある。
働き方の選択肢は確かに広がった。しかし、その働き方で理想のライフスタイルを実現することや、それによって多くの収入を得ることは、自身の意識をアップデートとすると同時に、今ある忙しい生活のなかで、新しい働き方を実現するための実践や学びに、多くの時間と体力を工面するというタフさも求められるのだ。
自由の構築には時間がかかる──だからこそ、焦らなくていい
副業を始めること、フリーランスになることは誰にでもできる。だが、それによって自由を構築することは多くの試行錯誤が求められる。時間も体力もかかる。
「私が自由に働けている」と感じたことは正直ない。いつでも大きなプレッシャーと帳簿に対してうんうん唸りながら対峙してきた。この働き方で真に感じられるのは、自由ではなく“柔軟”なのかもしれない。
独立してから10年近い年が経った頃。保育園で体調を崩した我が子を、誰に気兼ねすることなく真っ先に迎えにいけた時、その恩恵の大きさを知った。家族のために働く時間や場所を柔軟に調整することは、大学卒業時も就職することなくフリーランスの道を継続すると決めた時の至上命題だった。ここまで本当に長かった。
「副業解禁=自由に働ける社会の訪れ」とは言い切れない。しかし、今までとはちょっと違う人生への扉はできかけているのかもしれない。大切なのは、その扉を開くのは自分、扉を開いた先の景色をデザインするのも自分であると認識すること。そして、焦らないこと。必ずしも扉を開く必要があるわけではないこと。あなたは新しい挑戦を「選ぶ」という選択肢も、あえて「選ばない」という選択肢も持っている。本業でのスキルアップや今ある生活の基盤を強固にすることが悪いわけなんてないのだから。
どうか無理なく。限りある日々を、ただただ大切に、大切に積み上げて。






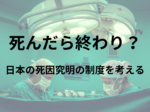



の看板-280x210.jpg)

-280x210.png)

-300x169.jpg)