
2021年、体外受精を通じて誕生した子どもの数が、前年より9,416人増加し、6万9,797人で過去最多となったことが日本産科婦人科学会の調査結果からわかりました。この結果は、学会が29日に公表しました。
2020年は新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、受診者数が減少しています。1986年に学会への報告制度が開始されて以降、初めて前年を下回る結果になりました。
国内全体の出生数は減少していますが、2021年には体外受精の治療件数が約45万件から49万8,140件へと増加。特に39歳の治療件数が最も多く、3万9,631件を記録し、40歳、41歳と続いています。
厚生労働省の統計「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」では、2021年における全国の総出生数は81万1,622人とされており、このうち11.6人に1人が体外受精により誕生しています。
2020年の総出生数と比較すると、13.9人のうち1人というデータから、体外受精による出生の割合が増加していることがわかります。2022年より、不妊治療が公的医療保険の対象となり、治療を受ける多くの人にとって経済的な負担が軽減される見込みです。
調査をまとめた東邦大の片桐由起子教授は、この傾向について「出生数が減少するなか、生まれてきた子どもの11人に1人が体外受精児となり、割合は増えている」とコメントしました。
ネット上では、「周囲を見ても、不妊に悩んでいる人がかなり多い」「公的医療保険も適用されるようになったのなら、利用したい人は今後もっと増えそうだ」などの意見が寄せられています。
体外受精とは?他の治療方法との違い
不妊治療として知られる体外受精は、卵巣から卵子を取り出し、その卵子と精子を体外で受精させて最も妊娠しやすい時期に子宮に戻す、という治療方法です。体外受精は他の治療方法と比べて、特に高い妊娠率が期待できるとのことです。
その主な理由として、受精までのプロセスを大幅に短縮できる点が挙げられます。具体的には、妊娠が完了するまでの多くのリスクを効率的に回避できます。
例えば、タイミング療法と呼ばれる方法では、全てのリスクを排除することは難しいとされています。また、人工授精の場合も一部のリスクを回避できますが、それ以外の点ではタイミング療法と同様であるとのことです。
その点、体外受精は複数のリスクをうまく回避し、妊娠率を向上させることが可能です。そのこともあり、2021年では体外受精を通じて誕生した子どもの数が過去最多となりました。






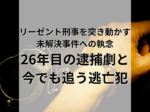


-280x210.png)


-300x169.jpg)