- Home
- コラム・インタビュー, ビジネス
- 【医師の論文解説】大学教授就任への戦略 大学教授の評価基準
-1024x576.png)
大学の教授になるためには特定の分野の学問を極める必要があります。また、それだけでなく、さまざまな業績をあげて社会に貢献することが重要とされています。
そんな大学教授はどのような指標で評価されているのか、また、その評価は適切なのかという疑問に応えるための研究が行われています。
今回は、大学教授に対する評価がどのように行われているかを調査した論文をご紹介します。
論文のタイトル
カナダモントリオールのマギル大学 Danielle B Rice氏らが2020年6月,BMJ(British Medical Journal)に報告しました。
研究の背景と目的
大学教員の昇進や、終身在職権を判断するための評価基準は、大学によって異なります。
従来は、どれだけたくさんの論文を出版しているか、どれだけ研究費を獲得しているか、また、国内外でどれだけ研究が評価されているかといった、研究面の業績を主体とした評価が行われていました。近年では、それに加えて、研究の質や社会への貢献度も加味して、評価をするべきだという声が高まっています。
しかし、まだまだ従来型の基準での評価が、多くの大学で行われているというのが現状です。今回の研究では、世界の主要な大学で、実際にどのような基準で、大学教員や教授の評価が行われているのかを調査することが目的となっています。
研究の方法
ライデン世界大学ランキング(オランダのライデン大学が発表する世界の大学のランキング)から、170の大学をランダムに選出しました。そのうち、生命医科学部を持つ146校が今回の調査対象になり、最終的期に92大学の評価ガイドラインが詳細に分析されました。
調査では、分析した評価基準を「従来型」と「非従来型」の2つに分類しました。
- 従来型の評価基準には以下のものが含まれます
- 査読付き論文の数
- 論文での著者順位
- 掲載された学術誌のインパクトファクター
- 研究費の獲得実績
- 国内外での研究評価
非従来型の評価基準には、以下のものが含まれます。
- 文の被引用数
- 研究データの共有
- オープンアクセスでの論文公開
- 研究の事前登録
- 論文発表ガイドラインの遵守
- 研究の社会的影響度(オルトメトリクス)
- 研究休暇制度への配慮
非従来型では、単に評価の高い医学雑誌にたくさんの論文を投稿するだけでなく、その研究結果で、いかに社会に貢献しているかを評価するものとなっています。
研究の結果
対象となった大学の評価ガイドラインを分析した結果、多くの大学が依然として、従来型の評価基準を重視していることが分かりました。
95%の大学が査読付き論文の数を重視しており、67%が研究費獲得を評価、48%が国内外での評価を考慮、37%が論文での著者順位を重視、28%が掲載誌のインパクトファクターを考慮、といった結果でした。
非従来型の評価基準をみてみると、
- 論文の被引用数:26%、研究休暇への配慮:37%、研究の社会的影響度:3%、データ共有:1%
- オープンアクセス出版、研究登録、報告ガイドラインの遵守:どの大学でも採用なし
ということでした。
この研究で分かったこと
今回の研究で、大学での研究者の評価システムは依然として、従来型の基準が使われていることが分かりました。これらの評価基準は、明確になりやすく分かりやすく評価しやすい一方で、以下のような問題点を孕んでいます。
- 研究の質よりも量が重視される。
- 短期的な成果を追求する傾向が強まり、長期間かけた研究の成果が評価されにくい。
- データ共有やオープンサイエンスなどの重要な取り組みが評価されない。
- 社会への実質的な貢献度が十分に評価されない。
このような状況を打破するために、非従来型の評価基準を積極的に導入して、より良い研究環境と社会貢献を実現するための評価システムの構築をすることが、今後の課題となりそうです。
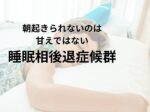



-150x112.png)




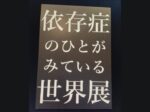








-300x169.jpg)