- Home
- コラム・インタビュー
- 「家族にも見捨てられた」一筋縄では行かない障がい者支援のリアルとは
「家族にも見捨てられた」一筋縄では行かない障がい者支援のリアルとは
- 2025/3/26
- コラム・インタビュー
- プロレス, 一般社団法人ガネーシャー, 北海道, 就労支援, 独自取材, 障がい者
- コメントを書く

障がい者と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか。
実際に接点が少ないと、「どう関わればいいのかわからない」「ちょっと不安」という気持ちを抱く人もいるかもしれません。障がいを持つ方々の多くは自活が難しく、障がい者支援施設を利用するケースが多いですが、その施設では、日々さまざまな問題が起きています。
暴力事件や突発的な問題行動など、その種類はさまざまで、最悪の場合は逮捕までいたることも。それでも一般社団法人ガネーシャー(以下、ガネーシャー)の代表・杉浦一生氏は「私たちが障がい者支援を諦めるわけにはいかないんです」と力強く語ります。
本記事では、ガネーシャーで実際に起きた事件をもとに「支援の現場ではどんなことが起きているのか」を詳しく掘り下げます。
<目次>
支援施設でのリアル。実際に起きた3つの事件

障がい者支援施設では特性や病気による症状で感情的になるケース、先を見通して物事を理解するのが難しいケース、理性の歯止めがきかないケースなど、その種類は多岐にわたります。
暴力事件
ある日、入居者の一人が他の利用者に暴力を振るい、被害者が顔を数針縫う大けがを負わせる事件が起きました。
掘り下げてみると、本人は両親との関係性が悪く、暴力は「言うことを聞いてもらうためのもの」であり、感情のコントロールがうまくできないことが課題でした。これにより、暴力に頼ることを覚えてしまい、他利用者とのトラブルも多かったようです。
店員暴行事件
ギャンブル依存症の傾向がある利用者が、外出中にパチンコ店を見つけて思わず入店。パチンコで負けたことに腹を立て、店員に暴行を加えるという事件を起こして逮捕されました。
普段の生活では落ち着いており、パチンコへの依存感も感じさせることはなかったものの、偶然街中でパチンコ店を見かけたことで歯止めが効かなくなったそうです。
詐欺グループ関与
未成年の利用者が闇バイトを始め、全国規模の詐欺グループに関与。他人のクレジットカードを使用してホテルなどを利用していたことが判明しました。その後、過去の余罪が多数発覚し、詐欺グループの一員として逮捕されました。
この利用者は児童相談所で保護されていた際、横のつながりからグループに誘われ、犯罪に手を染めたと言います。
このような事件に見舞われながらも支援を続ける杉浦さんですが、本人の特性よりもむしろ「根底にあるのは心のスキマ」だと指摘します。
障がい者が抱える心のスキマ。孤立をさせない支援の仕方

障がい者が抱える「心のスキマ」それは、過去のさまざまな体験によるものです。
トラブルが起きる時には『どうせ追い出すんだろ』『どうせ俺(私)のことなんてわかってくれないんだろ』という言葉が頻繁に聞かれるといいます。
「人の気持ちなんて完全に理解するのは不可能です。だから『わかるわけねぇだろ』って言い返します(笑)でも追い出したりなんてしません。外に出て困るのは私たちではなく本人なんです。なので、本人が出ていきたいと思うなら、自立するために何をするべきか考えるよう伝えます」
実際、家族関係の悪さから、家族から見捨てられるように施設に送られ、社会性を身に着けられないまま、トラブルを起こしては退所を繰り返して、孤立していくという悪循環に陥る利用者は多いのだそう。
「暴力をふるう行動も、今までそうしなければ生きてこれなかったという事実でもあるんです。虐げられてきたからこそ自分を守るための行動だったといえるかなと」と杉浦氏は分析します。
ガネーシャーでは、この心に空いた穴に着目し、ガネーシャーだからこそできる心のスキマを埋める支援を続けています。
「ガネーシャーなら、人と関わることが苦手な利用者でも、町内会の行事や温泉の清掃を通じて『誰かの役に立っている』という実感を得られます。これは、ただ施設の中で守られるだけでは得られない経験です」
田舎ならではの狭いコミュニティだからこそ人と関わる機会が増え、人間関係で嫌な思いをしてきた利用者も、成功体験を積み上げていける環境が整っているとのこと。
実際に利用者が地元の方々と浴室でばったりと会い、裸の付き合いで交流をすることも。最初は「障がい者」という悪いイメージから懐疑的な目で見られていたなかで、地道に交流を積み重ねた結果、今があるといいます。
人としての対話を重視。本人だけで生きていける力を身に付ける

障がい者支援の現場では、ただ手を差し伸べるだけでは問題は解決しません。時には厳しく指導し、本人が社会で自立できるようなスキルや考え方を身につけることが重要だと杉浦氏は指摘します。
「一般的な施設では、本人の生活が崩れる事を心配するから優しい発言しかしない。でも、それで伝わらないなら意味がありません。支援とは優しい言葉を伝えるのが目的ではなくて、本人が自立して社会を生き抜く力を身につけることなんです」
この考えから、対話を重視して、ストレートな言葉で伝えている杉浦氏。過去には言葉尻を取られて虐待を主張した利用者もいたと言いますが、それでもスタンスを変えずに、フラットな関係で対話をすることを心がけているそうです。
「世の中、理不尽はあるし『愛をもって接する』とか『許し合う』だとか、そういう綺麗事だけでは解決できないことがたくさんあります。だからこそ腹を割って話すことができればと思っています」
支援とは、本人が自分の力で生きていくための準備をすること。それを実現するために、ガネーシャーでは「厳しさ」と、それ以上の深い「愛情」を持って支援にあたっています。
ガネーシャーは最後の砦。偏見のない世界を諦めない

障がい者支援の実情を話しながら、杉浦氏は「見捨てずに支援をする必要性」を熱く語りました。
「本人は反省しているのに『厄介事を起こしたから出ていってください』では、いつまでたっても自立なんかできません。本人の悪いところは伝えて、粘り強く支援をしていきます。特にガネーシャーは最後の砦のような場所なので」
ガネーシャーは、杉浦氏が元プロレスラーであることを生かして一般的な支援施設では対応しきれない暴力行為についても対処できる数少ない施設です。そのため、他の施設から追い出された人々が居場所を求めてやってくるといいます。
もう後がない。他に行ける場所がない。そんな人々の居場所を守るため、ガネーシャは最後の砦として、決して支援を諦めないのです。

現在、ガネーシャーでは、障がい者と触れ合う機会を増やすためのプロジェクトを進めています。
養鶏場や食品工場が2025年の夏ごろにオープン予定で、ここで新たな雇用や社会参加、一般の方と交流の場としての機能を考えています。
商品のプリンを作ったり、観光場所を案内する役でガネーシャーの利用者を選び、実際に関わって「障がい者だと、言われないと気づかなかった」という状況を作るのが狙いです。
「障がい者の特性を完全に理解してくれなんて言う気は全くないんです。ただ、こういう世界があること、その一端だけでも知ってもらえればいいなと思います。知らないことは恐怖になるし、1%でも認知してもらえれば少しでも偏見は減るかなと思うんです」
”いつか偏見のない世界に”
偏見のない世界を作ることは簡単ではありません。ですが、まだ知らない世界をほんの少しだけでも知ることで、理解が一歩前に進めると話す杉浦さん。
ガネーシャーの支援は、その『一歩』を増やすために続いています。

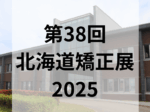






-150x112.png)

-150x112.png)

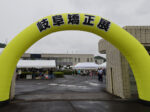

-280x210.png)



-300x169.jpg)