- Home
- コラム・インタビュー
- 埋もれた名著を救い出せ!読書系インフルエンサー・ぶっくまが起こす出版業界イノベーション「本をつなぐプロジェクト」
埋もれた名著を救い出せ!読書系インフルエンサー・ぶっくまが起こす出版業界イノベーション「本をつなぐプロジェクト」

「紙の書籍の売上が減少している」「街の本屋さんが次々消えていく」…出版業界に関する暗いニュースを聞いたことがある人も多いでしょう。そんな厳しい状況にある出版業界を、SNSを通して盛り上げようと奮闘しているのが、「本をつなぐプロジェクト」の代表・ぶっくまさんです。
「SNSから出版業界にイノベーションを起こしたいんです」と静かな熱意を込めて語るぶっくまさん。「本をつなぐプロジェクト」は一体どんな取り組みをしているのか、活動内容や立ち上げのきっかけを伺いました。
<目次>
「おもしろい本なのに、読者のもとに届かない」現実

プロジェクトの始まりは、ぶっくまさんが著者として経験した危機感に端を発します。プロジェクトを立ち上げる前年である2024年、ぶっくまさんは読書術に関する著書『「知る」を最大化する本の使い方』(翔泳社)を出版。自身が本を出版する立場になったことで、著者の力だけで本を広めることは難しいと痛感したそうです。
「一般的に本は出版社から書店に配本され、書店の棚に並べられた後、読者が購入して手に取るという流れで流通しています。しかし書店に置いてもらえる本の数には限りがありますし、新人ともなれば、ますます書店に置いてもらう機会は少なくなるでしょう」
素晴らしい本であったとしても、そもそも読者の目に触れる機会すらないことがある。この現状を目の当たりにしたぶっくまさんは、本の流通システムに対して強く問題意識を持つようになったといいます。同時に、SNSの力を活用すれば、この状況を打破できるのではないかという考えが浮かびました。
X(旧Twitter)で読書に関する情報を発信しているぶっくまさんは、当時Xで約7.5万人・SNS全体では9.5万人のフォロワーを抱えていました。日々さまざまな書籍を紹介するなかで、ある書籍のポストが「1.9万いいね」「表示回数700万回」のバズりを起こし、その書籍がAmazonの総合ランキングで最高7位になる経験があったのです。
SNSの力を生かせば、埋もれてしまうはずだった本を救えるのではないか。このアイデアから、彼の挑戦が始まりました。
セミナー参加から生まれた熱の連鎖

ぼんやりとしたアイデアが確かな輪郭を持ったのは、「発信する勇気」(きずな出版)の著者、末吉宏臣さんのセミナーに参加したときのこと。セミナーのワークで「自分は何をしていきたいのか」を深く掘り下げていくと、ぶっくまさんの中で「2つのベクトルがカチッと音を立てて結びついた」といいます。
1つは、これまでの人生で何度も「本に救われてきた」という感謝の念。もう1つが、著者として出版社や書店と関わった経験や、そこで感じた課題。この2つが噛みあうことで、ぶっくまさんの頭の中にはマインドマップが広がっていったそうです。
「SNSが中心となり、そこから著者、読者、出版社、取次といった、本に関わるあらゆる立場の人々へと枝が伸びていくイメージです」
このつながりを通じて、本が埋もれてしまう課題を解決したい。さらに、自分たちの活動から生まれる「熱」を伝えることで、本から離れてしまった人たちにも興味を持ってもらい、出版業界を盛り上げたい。そんな願いを『本をつなぐ』という言葉に込め、読者・著者・出版社・書店・レビュアーなどをつなぐプロジェクトが生まれたのです。
この熱い構想をセミナーで打ち明けると、講師の末吉さんから「すごい!可能性を感じますね!」と力強い言葉が返ってきました。その言葉に背中を押され、ぶっくまさんはXでコンセプトを発信。すると、出版業界に従事しているもんきちさんはじめ、同じ志を持つ仲間たちから「一緒にやりたい!」と熱い反応が次々と集まってきたといいます。
本を愛する人たちの熱い想いは、ぶっくまさんの決意をより強固なものにしていきました。そして2025年1月、ついに「本をつなぐプロジェクト」がスタートしたのです。
本に関わるすべての人をつなぐために。プロジェクトを支える3つの柱

「本に関わるすべての人をつなぐ」をコンセプトにスタートした「本をつなぐプロジェクト」。現在の活動は、3つの取り組みを軸に展開されています。
① 熱量を届ける書評チーム「ツナグ図書館」
「ツナグ図書館」は、本を愛するレビュアーが集まり、SNSで書評を発信するチームです。
「初めて現実の書店に『ツナグ図書館』のコーナーができたときは、夢のように思えてしばらく見入ってしまいした。読書家としてこれほど光栄なことはありません」
SNSで本の魅力を熱く伝えることで、読者が自分の求める本と出会うきっかけをつくる。読者が書店に足を運び、著者や出版社が届けたい本を手に取ることで、結果的に書店にも喜んでもらう。読者、著者・出版社、書店の「三方よし」の関係を築くことが、「ツナグ図書館」の目的だとぶっくまさんは語ります。
「ツナグ図書館」の活動は着実に実を結び、現実の書店に専用棚が設置されるという大きな成果につながりました。SNS上の活動が、現実の書店の景色を変える。その手応えが「本をつなぐプロジェクト」の活動をさらに加速させました。
② 本音でつながる「正直読書会」
「正直読書会」はXのスペース機能を使い、少人数で本について語りあう不定期のオンライン読書会です。
Xのスペースという音声配信を利用し、忙しい人でも耳から本に関する情報を受け取れるようにすることを目指しています。ぶっくまさんは「本に関する『生』の気持ちをお届けすることで、読者と本をつなぐきっかけにしたい」と語ります。
③ 読者が主役の「SNS推し本大賞」

「SNS推し本大賞」は、読者の「推したい!」気持ちを起点にした、読者の投稿だけで選ばれる新しい本の大賞です。「誰もが参加できるSNSの力で新たなベストセラーを生み出したい」と、ぶっくまさんは情熱を込めて語ります。
SNSで「推し本」を募集したところ、第1次選考の締め切りである6月7日が近づくにつれて右肩上がりに応募が増え、「#SNS推し本大賞2025」のハッシュタグ利用は1,700件、そのうち有効票は1,200件を突破。SNS上では、参加者の熱い「推し語り」が日々繰り広げられていました。
「このままでは期待に応えられない」成功の裏で生まれた新たな課題

プロジェクトは順調に拡大し、各所で大きな成果を上げています。一方で、ぶっくまさんは次なる難題を抱えていました。
「全国の書店で棚を展開していただくなど、本当に多くの人に応援していただいています。でも、そのご期待に『本をつなぐプロジェクト』自体のブランディング強化が追いついていないのが正直なところです」
このままでは、皆さんの厚意に応えられないのではないか。そんな危機感を常に感じていると、ぶっくまさんは率直に語ります。また、協力してくださる出版社や書店を増やすための営業活動にも頭を悩ませているといいます。
「今までほとんど営業をしたことがなく、手探りの状態なんです。それに週3日は他の業務に時間を使う必要があるので、アポイントを取って出版社さんや書店さんを回る時間に物理的な制約があります」
しかし、新たな壁にぶつかりそうになるぶっくまさんには強い味方がいました。自身が信じて積み重ねてきたSNSの力です。
「私が続けてきたSNSでの発信を知っている出版社さんや書店さんが、思った以上に多いんです。出版社さんや書店さんを訪問すると、『ぶっくまさんですね』と温かく迎えられることもあるんですよ」
SNSから出発して、現実の書店や出版社に応援の輪が広がり、活動が好循環で回り始めている。その確かな感触が、ぶっくまさんに「このプロジェクトは間違っていない」との自信を与え、活動を続ける力になっているのです。
本が届ない現実を変えていく。リアルに広がるSNSの力

SNSというオンライン上のつながりを越えて、現実世界に影響を与える存在となった「本をつなぐプロジェクト」。プロジェクトの今後の展望を、ぶっくまさんに伺いました。
「今後も、本が好きな人はもちろん、これまであまり本に触れる機会がなかった人にとっても心躍る情報を発信していきたいですね。そして、できるだけ多くの人と一緒に、本を通じて新しいつながりを広げていけたら。こんなにうれしいことはありません」
そう語るぶっくまさんが、心からうれしそうな表情をしていたのが印象的でした。本に関わるすべての人をつなぎたい。揺るぎない信念を胸に抱き、志を同じくする仲間たちとともに、ぶっくまさんはこれからも新たな挑戦を続けていきます。




-150x112.png)





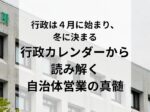


に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)

-300x169.jpg)