- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 島津義弘と戦国時代の医学
-1024x576.png)
医学は日々進歩がめざましく、私たちはさまざまな医療を受けることができます。
新薬が日々開発されており、多くの疾患を内服で治すことができますし、外科手術の技術も発達しています。多くの人が医学の恩恵を受けているのです。
そのような時代を生きていると、医学がまだ発達していなかったような時代の人の姿を想像するのは難しいかもしれません。
しかし、すでに戦国時代には、伊達政宗が手洗いを推奨していました。
また、金創医術と呼ばれた、外科的処置が戦場に出る兵士たちに対して行われていました。
金創医術は平安時代末期に誕生したと言われおり、「金創」は刀傷を表します。
すなわち外科医です。
この金創医術を、武将の立場でありながら習得していたのが島津義弘です。
今回は、島津義弘と金創医術について紐解いていき、戦国時代の医療を覗いてみましょう。
島津義弘とは
島津義弘は、戦国時代~江戸初期の武将です。
天文(てんぶん)4年7月23日(1535年8月21日)生まれ。
島津家の一族として、数々の戦で輝かしい活躍を見せました。
特に、関ヶ原の戦いでは、その際立った勇猛さから「鬼島津」として、JR伊集院駅前に銅像があるように、広く知られるようになりました。
「鬼島津」の由来は、戦場で見せた勇敢な戦いぶりと圧倒的な存在感に由来しています。
敵に対する果敢な攻撃と巧みな戦術に長けていたため、その名が日本の歴史に深く刻まれています。
また、彼のリーダーシップと戦略的な思考は、後世の軍事指導者たちにも多大な影響を与えました。
敵陣に果敢に攻め込む「鬼島津」でしたが、心根は優しく、慈悲深かったと伝えられています。
戦いが終われば、敵味方の区別なく鎮魂の儀式を行い、味方に対しては身分や階級を超えて家臣と団結するリーダー型の武将であったと言います。
島津義弘は「金創医術」を習得していたのですが、そのような優しい性格の持ち主が目の前で家臣が命を落とす戦場を見る生活を送っていれば、人を救う技術を修めようと考えるのも自然の流れなのかもしれません。
島津義弘の金創医術
戦国時代の医学は、まだまだ今のような根拠に基づいた医療を実践できるような状態ではなく、迷信や祈祷に近い医療も行われていました。
また、ヨーロッパから南蛮医学がもたらされつつあった時代でもあり、漢方薬などの薬を使った治療なども行われ、玉石金剛の発展途上の時代だったと言えます。
そのようななかで「金創医術」では、戦場で起こる刀や弓矢、鉄砲による傷に対して外科的な処置が行われていました。
南北朝時代の戦乱期に、先頭に従事した僧侶が施した医療を基にして生まれた金創医術は、全国的な戦乱で怪我人が大量発生していくなかで需要が増加し、多くの治療が行われるなかで体系化されていきました。
「戦国時代の外科医?ちゃんとした手順で治療をしていたとは思えないなぁ、酒を口に含んで、吹きかけて消毒とかしていたんじゃないの?」
なんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、現代の医師も馬鹿にできないくらいしっかりと手順を踏んで治療がされていたようなのです。
怪我人の治療にあたる際には、まずはじめに気つけ薬を使用して、落ち着かせてから止血を試みます。
そして、その傷を消毒してから必要に応じて縫合し、化膿止めの内服も行われていたようなのです。
現在の外科医が行なっている創傷治療と大まかな流れは変わりません。
戦乱のなかで生まれた金創医術は、平和な時代になっていくと産科的処置にも応用されるようになります。
島津義弘は、この金創医術を高度に使いこなしていたそうで、鉄砲の弾抜きや傷の洗浄はお手のものでした。
島津は、出産関係の知識も金創医術から得ていたとのことです。
さらに、痛みを和らげる呪術医の知識もあることが知られています。
つまり、戦場を束ねる武将でありながら、外科医であり、産婦人科医であり、精神科医であったとも言えるのです。
優しさだけではとても習得できない内容で、戦場での家臣の様子を目の当たりにし、強い思いを持って研鑽を詰んだことが想像できます。
このような武将であればこそ、兵士たちに慕われ、強固な戦闘集団を形成したのでしょう。
まさしく、スーパー武将と呼ぶにふさわしいと言えますね。
85歳で天寿をまっとうしましたが、義弘の死に際して、殉死禁止令が出ていたにも関わらず、何人もの人が殉死したそうです。
戦術と医術に長けた島津義弘
今回は、戦国武将・島津義弘と金創医術について見ていきました。
戦国時代は、全国で多くの怪我人が出ただけあって、外科的な処置が発達した時代でした。
そのような戦乱期を生きた武将である島津にとって、医術が大いに役立ったのは想像に難くありません。
参考文献:
1.乾俊秀,松本佑子.「たなべや薬」は島津義弘の秘薬か? 処方・効能に基づく考察.薬史学雑誌 2019;54:24-30
2.井上清恒.南蛮医学の展開.昭和医学会雑誌 1972;32:517-524
3.森田まゆ,鈴木達彦.日本における金瘡治療の展開. 日本医史学雑誌 2010;56:458-459
4.小林清治. 『伊達政宗』.吉川弘文館.東京1959
5.戦国歴史研究会. 『島津義弘―慈悲深き鬼 (戦国闘将伝)』.PHP研究所.東京 2008



-150x112.png)




-150x112.png)


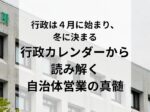



の看板-280x210.jpg)
-280x210.png)

-300x169.jpg)