- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 脳死ドナーの大切さ 命のリレーにあなたも参加しませんか?
-1024x576.png)
脳死ドナー登録、していますか?
こう聞かれて「しています!」という方はかなり少ないでしょう。
では、もしあなたの大切な家族や友人が「移植」でしか助けられない疾患になったら、きっとこう思うはずです。
「なぜ、みんなもっと『ドナー登録』しないんだろう」と。
私たちの体内には、誰かの生命を救う可能性が秘められています。
それが、脳死ドナーとなることでの臓器提供です。
たとえ、私たちが生を終えても、私たちの中に宿る命は、他の誰かに新たな生を与えることができます。
それはまさに、生命のバトンタッチです。
しかし、その大切さを理解し、脳死ドナーとして登録する人はまだまだ少ないのが現状です。
では、なぜ脳死ドナー登録は少ないのでしょうか?
今回は、そんな脳死移植の現状と脳死ドナーになることの大切さについて解説していきます。
脳死移植とは?
脳死とは、私たちが自分自身で思考したり、感じたりするための大切な器官である「脳」が完全に機能を停止した状態のことです。
そして、脳死移植とはその「脳死」になった人から、必要とする人へ臓器を移植することです。
この脳死とは、医学的には「死」の状態を指します。
つまり、心臓はまだ動いていても、自分で呼吸ができなくなり、脳が全く動かなくなる状態です。しかし、その体の中の他の臓器は、まだきちんと働いている場合があります。
例えば、脳出血や脳梗塞などの脳に関する疾患や、交通事故などで頭部外傷があった場合などです。
そのような場合、例えば「心臓」「肺」「肝臓」「膵臓」など、さまざまな臓器を必要とする人へ移植することができます。
ただ、想像してみてください。自分の大切な人が脳死になってしまったとき、その人の臓器を他の人に譲るという選択は、とても難しいことかもしれません。
「まだ脳死は死とは認めるのに抵抗がある」
「最期をバラバラにされるのはいやだ」
「死はきちんと臓器がそろったきれいなままの姿でいてほしい」
そんな考えが出てくるのは至極自然なことです。
しかし、逆に考えてみてください。あなたやあなたの大切な人が、どうしても臓器が必要で、それがなければ生きていけない状態になったらどうでしょう。その時に、誰かが自分の臓器を提供してくれることで、あなたやあなたの大切な人の命が救われる。それが「脳死移植」なのです。
日本の脳死移植の現状は?
まず、日本の脳死移植の現状について考えてみましょう。
実は、日本で臓器移植を必要としている人は約15,000人います。しかし、1年間で移植を受けられる人はわずか400人。つまり、待っている人の中で手術を受けられる人は、2~3%しかいません。この数を見ると、どれだけ多くの人が必要な臓器を待っているかが分かりますね。
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
| 現登録者数 | 884人 | 533人 | 343人 | 13,757人 | 160人 | 9人 |
| 内、 心肺同時 | 5人 | 5人 | – | – | – | – |
| 内、 肝腎同時 | – | – | 30人 | 30人 | – | – |
| 内、 肝小腸同時 | – | – | 0人 | – | – | 0人 |
| 内、 肺腎同時 | – | – | – | 134人 | 134人 | – |
実際、移植を受けた人の平均的な待機の期間として、心臓は約3年、肝臓は約1年、肺は約2年半、膵臓は約3年半、小腸は約1年となっています。特に、待機者の多い腎臓移植は、約15年となっています。
15年、腎臓が不自由な状況で待ち続けられますか?
これも深刻な「ドナー不足」の影響です。
さらに、日本と他の国を比べると、日本の臓器提供者数は他の国よりも圧倒的に少ないです。例えば、アメリカでは、人口3億3,200万人に対して、年間約1万4,000人が臓器を提供しています。
それに対して日本では、人口1億2,000万人に対して、年間100人前後しか臓器提供をしていないのです。
そして、1999年から2023年5月11日時点で、脳死移植提供例は953例にしか過ぎず、実際の移植件数は、以下のようになっており、953人の尊い「善意」からこれだけの命が救われています。
- 心臓:752例
- 肺 :801例
- 肝臓:801例
- 膵臓:73例
- 腎臓:1,212例
- 小腸:29例
世界から見ても、日本の脳死移植の現状は悲惨な状況ですが、それでも脳死移植によって確実に多くの命が救われています。
代わりに日本では、生体肝移植すなわち健康な人から肝臓の一部を取り出し、臓器を受け取る患者様(レシピエント)に移植する手術が、年間400例行われている現状があります。
筆者の所属していた小児医療センターでも行われていた手術ですが、健康な人の体にメスを入れることは大きな負担となります。
なぜ日本で脳死移植は進まないのか?
では、なぜ日本で脳死移植は進んでいないのか。大きく分けて4つの問題があげられます。
①臓器提供や移植を行うことができる施設が限られるから
まず1つ目の問題は、臓器提供を行うことができる施設が限られることがあげられます。
実際、臓器提供できる施設は全国の施設のうち、わずか32%しかありません。
これは、脳死判定ができる専門の医師や、ICU(集中治療室)での管理など、たくさんの手間と時間がかかるため、中規模の病院ではなかなか取り組むことが難しいからです。
さらに、臓器移植ができる施設となるともっと少なく、大学病院レベルのごく限られた施設でしか移植を行うことができません。
少し想像してみてください。いつ「脳死」がおきるかなんて誰も予測できないですよね。つまり、移植医師は、24時間体制で脳死のコールを待っている状況です。
しかも夜中であろうと何時であろうと、ひとたびコールされると、脳死を待っている患者さんや家族への電話、臓器が適切に使えるかどうかの確認、ICUや手術室への連絡、移植チームの立ち上げが分単位・時間単位で行われます。
そして、臓器を摘出するまでの時間を綿密に計算しつつ、すぐに搬送されたら移植できるように、緻密に計画を練りながら手術を進めて、速やかに臓器を移植する。
これだけのことをするには、相当な数のスタッフやコーディネーターの労力が必要であることが分かりますよね。どの施設でもできることではありません。
②「脳死」に踏み切れない場合があるから
2番目は、医師の意識の問題です。
救命救急医や脳神経外科医は、患者を救うことを使命としているため、目の前の患者の臓器を提供することは「負け」を意味すると考えてしまう場合があります。
医師はどうしても「目の前の命をなんとか救いたい」と思うもの。諦めたくないんです。
最後の最後まで頑張ろうと死力をつくします。医師も人ですから感情が入ると、客観的な判断が鈍る場合もあるでしょう。そのため、医師によっては「脳死」と認める判断が遅くなってしまうことがあるのです。
ただし、もちろん施設によっては、きちんと適切に脳死かどうかを判断し、患者の権利を守るために積極的に提供を行っているところもあります。
③ドナー家族の意識の問題
何よりも大きいのがこの3つ目、家族の意識の問題です。
まず、脳死自体が一般的に理解されていない場合があります。
脳死とは、脳全体の機能が完全に停止し、二度と戻らない状態を指します。
しかし、脳死の状態でも、人の体は心臓が動いていたり、体温を保っていたりするため、本当に死んだのかと疑問に思う家族も少なくありません。
さらに、家族がドナーになることを決定するには、悲しみやショックから立ち直り、様々な情報を冷静に理解し、そしてそれを受け入れる必要があります。
これは、時間的にも精神的にも大きな負担です。
しかも、急に脳死にいたった場合、受け入れるだけの十分な時間もありません。
医師からの情報提供はもちろん重要ですが、それだけではなく、家族を支え、ガイドする役割を果たす専門家も必要とされています。
また、ドナー家族の中には、臓器提供が「自分たちの大切な人を傷つける」と感じる人もいます。家族にとって、「提供された臓器が他の人の命を救う」と言われてもピンと来ないし、「傷つける理由にはならない」と思ってしまう方もいるでしょう。
これらの問題を解決するために、厚生労働省や学会なども動いています。
例えば、脳死判定ができる場所への搬送が可能になるように議論が進められていたり、家族に寄り添うメディエーターという専門職も作られていたりします。
しかし、まだまだ課題は多く、日本での脳死移植が進むためには、さらなる取り組みが必要です。
参照:
東洋経済「なぜ巨費でも米国へ?「臓器移植」日本で進まぬ訳」
NHK「“臓器移植”について語りやすい世の中に」
④臓器移植の制度の違い
国ごとの臓器移植に関する制度の違いも影響をします。
制度には大きく2つあり、一つは、アメリカ、ドイツ、韓国のように本人が生前、臓器提供の意思表示をしていた場合、または家族が臓器提供に同意した場合に、臓器提供が行われるOPTING INという制度です。
もう一つは、イギリスやフランス、スペインなどの本人が生前、臓器提供に反対の意思を残さない限り、臓器提供をするものとみなすOPTING OUTという制度です。
世界の臓器提供数を人口100万人あたりの臓器提供者数として世界の国々と比較すると、日本は0.62であり、アメリカの1/68、韓国の1/14に過ぎないことから、他国と比較して臓器の提供件数が少ないといえます。
人口の少ない国でもOPTING OUTの制度で取り組む国は、提供数が多くなる傾向があります。
なお、どちらの制度の場合も実際には家族の反対があれば臓器提供は行われません。
参照:日本臓器移植ネットワーク 世界の臓器提供数(100万人当たりのドナー数)
「命をつなぐ」脳死移植をさらにつなげるために
脳死移植の現状、なんとなく理解できましたか?
私たち一人ひとりの選択が、誰かの命を救い、希望をつなげるキーとなります。
脳死ドナーになることは、自分の生命が息を引き取った後も、他の人々に生きる希望を与える大切な選択なのです。
だからこそ、脳死ドナーについて理解し、自分自身がどうしたいのかを考え、そしてその意志を伝えることが大切です。
命のリレー、あなたも一緒に参加しませんか?
あなたの選択が、命をつなげ、未来を開く一歩となることを信じています。
参考文献:
- 田村純人. 移植の国際状況:『移 植』2021:56:165-183
- Dubernard JM, Petruzzo P, Lanzetta M, et al. Functional results of the rst human double-hand transplantation. Ann Surg 2003:238: 128-136
- Declaration of Istanbul Custodian Group. 臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言2018 年版(日本語訳)(2023.05.15取得)



-150x112.png)


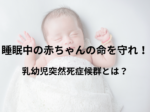
-150x112.png)





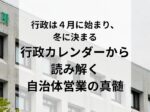

-280x210.png)


-300x169.jpg)