- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 子どもにガーデニングは必要?園芸がもたらす非認知能力について
-1024x576.png)
多くの親御さんが、自分の子どもは社会で活躍できる人になってほしいという願いを持っていると思います。
社会に活躍できるようにするために、まずは勉強をたくさんして学力を上げるという方法が思いつくのではないでしょうか。
もちろん学力は大事なのですが、学力以外にも大事な能力があります。
その学力以外の能力を上げるために、園芸に取り組むのが効果的であるという報告があるのです。
今回は、社会に出るうえで必要な学力以外の能力についてと、その能力を伸ばすために有効な園芸について解説します。
認知能力と非認知能力
「能力」という言葉を聞くと、多くの人が学力テストなどで測れる能力を思い浮かべるのではないでしょうか。
知能検査で測定できるような能力のことは、「認知能力」と呼ばれています。
一方で、今取り組むべきことに意欲を持ったり、自分の行動に自信を持ったり、辛いことを耐えたり、自制したり、他者に共感し強調したりといった、精神的な成熟度に関わるような能力のことを「非認知能力」といいます。
コミュニケーションや自制心に代表されるこれら非認知能力は、発達障害の子どもや大人にみられる偏りや特性ともなります。
依然として就職に学歴がかなり重要な要素となっている我が国ですが、近年、認知能力を追い求める教育への反省という意味も込めて、この非認知能力への注目が高まっています。
例え、認知能力が高くても、非認知能力が低いと、周りの人と協力して仕事をしたり、難しい課題に挑戦する気持ちを失ってしまったりして、うまく活躍することができないのです。
参考:小塩真司. 「非認知能力」の諸問題. 教育心理学年報2023;62:165-183
非認知能力を伸ばすために園芸が有効な理由とは
非認知能力は、マニュアル通りにいかない課題に取り組んだり、他の人と協力する経験をしたりすることで伸びていきます。
また、幼少期に自然に接することや地域に接することが有効である、という報告もあります。
園芸は、これらの条件にぴったりと当てはまっており、かつ、家庭でも比較的気軽に取り組むことができるという特徴があります。
園芸はまさに、非認知能力を伸ばす、発達障害の療育にうってつけな課題であるといえるでしょう。
参考:奥村咲,池田琴恵. 大学生の非認知能力と関連する幼少期の体験の検討.東京福祉大学・大学院紀要 2020;3:155-165
身近なようで身近ではない園芸
園芸の現状についてみてみると、2011年の統計で職業として園芸を行っている「農業従事者」は約102万人です。
これは、同年の生産年齢人口の1.8%と、ごく少数になっています。
現代社会において、農業はもはや身近なものではなく、どこかの誰かがやってくれているものという印象になってしまっており、野菜や米を育てることについて、知識を有している子どもは多くないというのが現状です。
また、暮らしの中の園芸についても、教育に関連して科学的に注目されることはあまりなく、趣味や娯楽、遊びにカテゴライズされ、一般の人と植物との関わりを研究した報告はあまりありませんでした。
園芸が、非認知能力を伸ばす課題として認識されてからの歴史は、まだまだ浅いのです。
園芸がもたらす非認知能力への無視できない影響
2013年に発表された研究で、女子大学生および園児の母親を対象に、幼少期の栽培体験が多かった群と少なかった群に分けて、トラブル処理、コミュニケーション、問題解決の能力を比較したところ、いずれも栽培体験が多い方の被験者の平均値が優位に高かったという結果が出ています。
これは、幼い頃から栽培の体験をする子どもは、家族や栽培を一緒に行う仲間とのコミュニケーションを経験していることで、共感やコミュニケーションなどの社会的スキルが発達したためであると考えられます。
幼児における栽培活動では、植物や自然に興味を持つといった自然に対する好奇心のみならず、親や友人などの集団との関わりから社会性と培うという重要な役割も果たしてくれます。
さらに、小学校でガーデニングと料理の授業を行うと、子どもたちの血糖値やコレステロール値が良好になるという研究結果が報告されました。
これは「過去20年間続けてきた、すべての運動の奨励や食生活の改善を促すという介入は、このガーデニング介入ほど効果的ではなかった」と結論づけています。
現在、幼少期に自然に触れる機会が少ない子どもも多くなっており、そんな中で自然に触れる機会を増やすことのできる園芸は、非認知機能を育むための格好の教材となるのです。
参考:
山本俊光. 子どもに園芸は必要か? 教育の視点から探る.農業および園芸 2013;88:82-95
Jaimie N Davis,Matthew J Landry,Sarvenaz Vandyousefi,et al. Effects of a School-Based Nutrition, Gardening, and Cooking Intervention on Metabolic Parameters in High-risk Youth: A Secondary Analysis of a Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open
. 2023 Jan 3;6(1):e2250375. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.50375
まずはお子さんと一緒に園芸を
今回は、子どもと一緒に園芸をすることのメリットについて解説をしていきました。
まだまだ学歴が重要な社会を生きる私たちは、ついつい認知能力を重視しがちですが、実際に社会のなかで必要とされるようになるためには、コミュニケーションや強調性、自制心や自信といった非認知能力が同じくらい重要です。
園芸を行うことで、この非認知能力を伸ばすことができるため、ぜひ自分のお子さんと楽しく園芸をやってみてはいかがでしょうか。



-150x112.png)





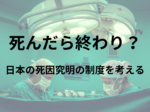
-150x112.png)




の看板-280x210.jpg)


-300x169.jpg)