
慶応義塾大学と米ワシントン大学の研究チームが3月21日に発表した国際研究「世界の疾病負担研究(GBD)」の分析結果によると、日本人の最大死因が2015年以降「認知症」となっていることが判明しました。
この調査は従来の国内統計とは異なるアプローチで死因を詳細に分類。例えば、がんを140種類に細分化するなど、より精緻な分析を実施しています。
結果として、医療技術の発展により脳卒中や虚血性心疾患が大幅に減少する一方で、認知症による死亡が増加傾向にあることが示されました。
特筆すべきは、2021年時点での日本の認知症死亡率が10万人あたり約135人と、イタリア(約108人)や米国(約60人)を大きく上回り、世界最高水準であることです。平均寿命は過去30年で5.8年延伸しましたが、健康寿命との差が拡大している現状も浮き彫りになりました。
日本の公的統計では誤嚥性肺炎や老衰が上位を占めるのに対し、この研究では認知症をそれらの根本原因と捉えています。東京大学の岩坪威教授は「認知症では嚥下障害が合併症として現れることが多く、寝たきり状態では誤嚥性肺炎などに繋がる場合がある」と説明しています。
この研究結果は、超高齢社会を迎えた日本における認知症対策の重要性を改めて示すものであり、予防と対応策の強化が急務であることを示唆しています。
日本人の平均寿命と健康寿命の乖離拡大 認知症対策の重要性高まる
今回の研究結果で注目すべきは、自立して生活できる健康寿命が73.8歳に伸びたものの、平均寿命との差が9.9年から11.3年へと拡大している点です。これは、健康を損なってから亡くなるまでの期間が長期化していることを意味し、介護や医療体制の重要性を示しています。
地域格差も浮き彫りになり、平均寿命が最も長い滋賀県(86.29歳)と最短の青森県(83.41歳)の差は約2.9年。この差は1990年当時(約2.3年)より拡大しています。
研究ではリスク要因も分析され、高血糖や肥満などの指標が近年上昇傾向にあることが判明。これらは認知症発症リスクとも関連するため、GBD日本の野村周平氏(慶応大特任教授)は生活習慣への注意が認知症対策に有効と指摘しています。
厚労省研究班によると、認知症高齢者は2050年に586万人に達する見通しです。高齢者の単独世帯増加と社会的孤立が認知症リスクを高める可能性があり、東大の岩坪威教授は「予防や医療体制の強化、患者が安心して生活できる環境整備」の必要性を強調しています。







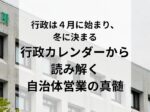
-280x210.png)

に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)

-300x169.jpg)