- Home
- コラム・インタビュー, 社会・政治
- 変わる日本の農業支援。福井県から読み解く農業従事者の育成と国の支援策

少子高齢化が進む日本において、農業の担い手不足は深刻な問題です。特に地方では、農家の減少が地域経済の縮小に直結しかねません。
そうしたなかで、六条大麦やコメの生産地としても知られる福井県では、農家の減少に直面しながらも、独自の支援策を通じて農業人材の育成と移住者の定着に注力しています。しかし、県独自の取り組みだけでは対応が難しい課題も多く、国による支援の必要性が高まっています。
コメの価格上昇によって農業への関心も高まっている今、本記事では縮小する農業にどう立ち向かうべきか、福井県をモデルに取材を行いました。
取材にご協力いただいたのは、福井県 農林水産部 園芸振興課 農業人材グループの主任・菅江 弘子氏と主任・水澤 靖弥氏、そして福井2区選出の衆議院議員であり、長野県泰阜村の政策アドバイザーや公益社団法人日本環境教育フォーラムの常務理事なども歴任し、移住と農業に精通している辻 英之氏です。
<目次>
若手の農業者を育てる福井県の挑戦。地域活性化の要「ふくい園芸カレッジ」とは
福井県は新規就農者の確保と育成を喫緊の課題と捉え、2014年には県立の農業人材育成機関「ふくい園芸カレッジ」を創設しています。まずは県の政策について福井県 農林水産部 園芸振興課へお伺いしました。
――ふくい園芸カレッジの試みについて教えてください
福井県が運営する「ふくい園芸カレッジ」では2年間にわたる実践的な研修プログラムを提供しています。これまで県内外から276名の卒業生を輩出しており、2023年時点でそのうち225名が県内に定着しています。簿記や経営に関する知識も習得してもらっており、地域農業を支えてくれるようになりました。
男女比はおおよそ男性8割、女性2割と男性が多いものの、毎年着実に女性の新規就農希望者も参加しています。県外からの移住者に対しては家賃の支援などの手厚いサポート体制を構築しているのが特徴です。
定着率が高い背景には、サポート体制に力を入れていることが挙げられます。就農前も就農開始後も、県・市町・JA等の 地域に根ざしたきめ細やかな支援を展開しています。今後も関係機関との連携をさらに強化していく予定です。
国の隙間を埋める福井県独自の支援制度
――福井県では、東京や大阪でも就農したい人を募っているそうですね
「農業を知りたい」「やってみたい」という声は多いのですが、実際に移住して就農しようとすると漠然とした不安があると思います。
そこで、「ふくい就農ナビ」というポータルサイトや県のHPなどで、就農へのステップなどをわかりやすく掲載しています。農業系のフェアに出展し、就農相談員が悩みや不安、福井県の支援策を丁寧にお話しするようにしています。ZOOMも活用しており、オンライン相談も可能です。福井県での農業や園芸カレッジでの研修をイメージしやすいように、制度や支援策、就農モデルプランなどをお伝えしています。
さらに、国の支援策に加えて、福井県独自の支援制度を整備しています。例として、国の事業では対象とならない50~60歳未満の県外出身者の新規希望者などに対して、県単就農給付金(準備型)を用意しており、年間90万円を最長2年間支給しています。
60歳未満の県外出身の就農希望者に対して研修奨励金として単身者には年間60万円(最長2年間)、家族連れには年間90万円(最長2年間)を支給しています。
福井県の単独事業である「未来に繋ぐふくいの農業応援事業」では、60歳未満の新規就農者を対象に、機械・設備導入などの初期投資に最大1,100万円を補助しています。
――今後の福井県としての課題はどのような点でしょうか
現在、県北部に位置する坂井地区での就農が半数以上を占めています。県内最大の園芸地区だからですが、奥越・丹南・嶺南といった他の地域へ新規就農者が流れにくいという地域偏在が発生しています。
この状況を打開するため、2028年1月に嶺南地区の拠点となる第2園芸カレッジを、美浜町にある県園芸研究センターに隣接する形で開設する予定です。これにより、県全体への新規就農者の呼び込みを強化し、県下全域での農業振興を目指します。
国がカバーしきれない部分への県単独予算の確保、園芸カレッジ卒業生のサポート強化も県政の課題です。福井県として地域に根差した具体的な戦略を立てながら、全県域に新規就農者が増えるように尽力していく予定です。
農家から寄せられる国への期待は「戸別補償制度」
農業を学べる「ふくい園芸カレッジ」を中心に、福井県では新規就農者を県内外問わずに増やしていけるよう、長期的な目線で事業を行っています。では、県がカバーしきれない課題や対策にはどのような点が挙げられるでしょうか。辻英之衆議院議員にお伺いしました。
――福井県を例に、国として感じている農業の課題にはどのようなものが挙げられますか
高齢化による担い手不足や耕作放棄地の増加など、農業を取り巻く課題は大小問わず山積みです。現在、国は食料供給に対する国内生産の割合を示す「食料自給率」ではなく、食料の潜在生産能力を示す「食料自給力」という概念の普及に尽力しています。この言葉を使用する背景には、農業や水産業などを中心に食料生産力を強化したいという意図があります。
しかし、多くの方がご存じのように、日本の食料自給力は農地の減少などにより低下傾向にあります。こうした状況のなかで、国として優先すべきなのは、現役で農業を支える農家の経営安定と、持続可能な農業の実現です。
私の選挙区である福井2区は、福井県の南側に位置する自治体が多く、農地の集積が進みにくい中山間地域が多く見られます。地元の声を拾うために隈なく歩いていると、現役農家の方々からは、「かつての『農業者戸別所得補償制度』のような安定した所得保障を復活させてほしい」との声が非常に多く寄せられています。
同時に、長期的な視点での新規就農者の育成強化が不可欠であるいう声が上がっています。こうした課題については次の参議院選挙の後に、与野党が連携して国全体で協議を深めていくべきだと考えています。
――「戸別所得補償制度」はなぜ農家から今も求められるのでしょうか
かつて旧民主党のマニフェストの目玉として打ち出された「戸別所得補償制度」は、農業の規模にかかわらず、すべての農家の経営所得を直接補償する仕組みでした。しかしこの制度は、「バラマキ」であるとの批判も受けました。
その後、自民党政権に移行してからは、制度の名称を「農業経営所得安定対策」と改め、生産性の向上や国際競争力の強化を目指す「攻めの農業」へと政策の方向性が転換されました。自民党政権下でも「経営所得安定対策」の一環として「米の直接支払交付金」は継続していましたが、支給水準を段階的に引き下げたのち、2018年度をもって終了しました。
しかし、現場の農家は営農規模の大小にかかわらず、天候不順や資材価格の高騰、不安定な市場変動など、常に大きなリスクを抱えています。やる気のある農家が大規模化や高付加価値化を進めるには、多額の初期投資が不可欠であり、そのリスクを軽減するセーフティーネットとしての戸別所得保障への期待は、依然として根強いものがあります。
先の衆議院選挙では、立憲民主党は民主党政権時代の「戸別所得補償制度」をバージョンアップさせた「農地に着目した新たな直接支払制度の創設」を公約に掲げ、一定の評価を得ています。国民民主党も「食料安全保障基礎支払」という新しい直接支払制度を提案しており、これが得票の伸びに貢献したと考えられます。
国としては今後も食料自給力、農地や農業従事者、とりわけ小規模農家を守るためにも大いに議論していくべきでしょう。
――人口減少や高齢化も重なり、農業従事者も減少しています。国としてはどのような対策が必要とお考えですか
私は政治家になる前に、長野県泰阜村で山村留学などの事業にNPOとして長年携わってきました。泰阜村は過疎化と高齢化に直面し、存続の危機が危ぶまれていた山村でした。しかし、NPOの活動で都市部の子どもたちを対象とした自然体験教育プログラムを展開した結果、村に年間数千人訪れるようになり、地域経済に活力を与えました。
この活動は子どもたちに教育を提供するだけでなく、地域住民を巻き込み、地域資源を活かした持続可能な仕組みをつくり上げる実践的な地域づくりです。都市と農村を結びつけ、交流人口を増やすことは、後々に移住・定住につながるとわかりました。かつて山村留学を経験した子どもたちが成長後に、家族を連れて移住してきたり、農業に従事するようになったケースも見られます。
こうした動きは1~2年という短期間で成果が出るものではなく、何十年もの長期的なサポートを経てようやく芽が出るものです。幼い頃に食物を自分の手で育て、それを自身や家族、周囲の人々が食べるという生きた経験を重ねると、食を産み出し続けてきた人へのリスペクトが生まれ「農家っていいな、やってみたいな」と思ってくれる人がようやく現れるんですね。
私の経験は小さな地域での事例ですが、いまや国として、こうした息の長い活動に全国規模で注力していく段階に入っているのではないでしょうか。コメの価格上昇や円安の進行による物価高騰などの影響で、食や農業の重要性を見直す動きが広がってきているので、今こそ大きな転機を迎えていると感じています。
「都市生活の食糧を支えているのは誰なのか」「生産者が生産そのものに集中できるように、経済的支援をすることがいかに重要か」その意義はこれまで以上に大きく、国会でも積極的に議論を深めるべき課題だと考えています。
福井県も県政が主体となり「ふくい園芸カレッジ」を中心とした農業人材の育成に継続的に取り組んでいます。嶺南エリアにも視野を広げることで、地域のさらなる活性化が期待できます。政権に左右されず、過疎地域における農業従事者への手厚い支援、農地を守る人々への継続的な支援など、長期的な視点に立ったサポートを今こそ国が実現すべきですね。










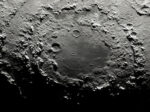







-300x169.jpg)