- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 子どもへの「教育投資」のリターンはどれくらい?新NISAとの違いを徹底比較
-1024x576.png)
新NISAがはじまって以来、日本では空前の「投資ブーム」になっています。
現に野村アセットマネジメントの資産運用研究所から報告された「投資信託に関する意識調査2024」によると、2024年は2022年から130万増加した3,976万人が投資家となっており、実に38%を占めています。
特に20代~40代での増加が顕著であり、投資をはじめたきっかけも「NISAを利用するため」が最多の36%となっていますね。
同時に、20代〜40代といえば、「子育て世代」の真っ只中。
男女共同参画局からの報告によると、日本人の初婚件数の最頻値は、男性で27歳、女性で26歳となっており、20代後半から結婚しはじめます。そして、厚生労働省の資料によると、2022年の日本の平均初産年齢は30.9歳。まさに子どもや結婚生活にお金をかけはじめるのも「20代〜40代」なのです。
ここでひとつの疑問が生じますよね。
一体、新NISAなどの投資にお金をかけるべきなのか、子どもにお金をかけるべきなのか。
最近は、子どもの教育環境も大きく変化しています。
偏差値の高い「頭のいい学校」に行くためには、塾に通うことが当たり前という状況が続いています。塾代も決して安いものではありません。
それこそ、子供の塾代が高すぎて、生活費を削っているというご家庭も多いことでしょう。そうなると、新NISAにお金をかけるのは夢のまた夢です。
では、純粋に経済学的に、子供の「教育投資」と新NISAはどちらの方が投資効率が良いのでしょうか。早速検討していきましょう。
子どもに「教育投資」をした場合の投資効率は?
まずはじめに、子どもに教育投資をした場合の投資効率について考えていきましょう。
今は、大学進学が普通の時代です。
2019 年の大学進学率は、53.7%と過半数に達しています。
男女別に見ると、2019年は男性が 56.6%、女性が 50.7%であり、男性の方が高いですが、過去30年の間にその差は縮まっています。
同時に、現在の日本は大学に入学しやすくなっています。
1990年の507校から2019年には786校へと、約30年間に55%増加しており、大学志願者数に対する大学入学者数(共に現役)で求められる「大学収容力」も1990年の52%から2019年には88%へと上昇しています。
そう、大学は入ろうと思ったら入れるのです。
そのなかで、仮にシンプルにするために「大学に入る」か「高校を出て働くか」というテーマで、教育投資する効率性を考えてみましょう。
当然、大学で勉強することを選んだ場合、大学での授業料がかかってきますが、ほかにも学校納付金、修学費、課外活動費、通学費などがかかってきます。
同時に、高校卒業後4年間働けば得られたはずの逸失賃金もあるでしょう。
日本学生支援機構調査では、大学4年間の学費合計額は、2018年平均で484万円であり、大卒者が就職直後に得られる賃金の 1.4 倍にも相当します。
一方、大卒者と高卒者との生涯賃金はどうなるか。
結論からいうと、就職直後から59歳までの賃金を合計すると、高卒者は2.0億円、大卒者は2.6億円であり、その差は「6,000万」にも上ります。しかも、退職金を加えると両者の差は一層大きくなるでしょう。
簡単にいうと、大学生活の4年間と484万を元手に「大学に行く」という教育投資を行うことで、生涯賃金の「6,000万」を手にしたことと同じことになるわけです。
すごいことではありませんか?
ここから大学教育投資の収益率を求めると、男性は6%、女性は8%と非常に高い水準となっています。
普通の大学でもこうなのです。いわゆる「一流の大学」「一流の高校」では、もっと生涯賃金は高まると予想されます。
さらに最近は、東京都や大阪府で行われた私立の高校に対する補助制度などを中心に、「いい学校」「いい大学」に入れるチャンスは増えてきている状態です。
もうひとつ、忘れてはならないメリットがあります。
教育投資には、子どもとの絆や子どもに目をかけてきた時間などがあり、これは新NISAでは表すことができないメリットです。
自分が年をとってくると、より一層大切になってくるのが、子どもや孫など下の世代との絆です。人生の終着点では、若いときのように動けなくなってくることは目に見えています。そんななかで、子どもが頼りになるのは、親としても誇らしいですよね。
また、税制的にも「教育投資」は効率がいいです。
教育費の回収は、子どもの給与で支払われることが多いので、もし投資の税金をかけられるとしても、給与所得控除が発生します。給与所得控除は、金融所得に発生する「一律20%」よりもずっと控除されますよね。
そう考えると、「教育投資」は経済学的に考えても、非常に悪くない選択肢のように見えてくるでしょう。
もしもリスクがあるとしたら、「子どもがどう成長するかわからない」という点です。
もちろん教育にお金をかけるほど、「いい大学」に入りやすいなどもあるかもしれません。
しかし、子どもも人間であり、どのように育つかは完全にはわかりません。お金をかけた分が回収できるかという点では、言いづらいところもあるでしょう。
また、教育投資では、親が投資をしても回収するのは「子ども」という点も注意です。
名義が異なるのです。
もちろん、子どものスネをかじろうと目論んで、教育投資を行う親はあまりいないでしょうから、「自分の資産を増やすだけ」が目的だとしたら、教育投資はあまり良い選択肢ではないでしょう。
ここでは、大学昼間部におけるお金についていくつか表にまとめました。
| 国立 | 公立 | 私立 | 平均 | ||
| 学費(円) | 授業料、 その他の 学校納付金 | 427,900 | 538,000 | 1,223,800 | 1,061,600 |
| 修学費、 課外活動費、 通学費 | 139,800 | 128,700 | 150,100 | 147,200 | |
| 小計 | 637,700 | 666,700 | 1,373,900 | 1,208,800 | |
| 生活費(円) | 食費、 住居・ 光熱費 | 553,600 | 428,000 | 321,100 | 367,200 |
| 保健衛生費、 娯楽‣ 嗜好費、 その他の 日常費 | 331,900 | 340,000 | 338,600 | 337,500 | |
| 小計 | 885,500 | 768,000 | 659,700 | 704,700 | |
| 合計(円) | 1,523,200 | 1,434,700 | 2,033,600 | 1,913,500 | |
| 2014年度 | 2016年度 | 2018年度 | |
| 学生生活費 | 1,862,100 | 1,884,200 | 1,913,500 |
| 奨学金受給者の割合 | 51.3% | 48.9% | 47.5% |
もしも新NISAを活用して投資をした場合は?
ガラッと変わって、新NISAを活用して、投資信託を買ったことを考えてみましょう。
新NISAとは、2014年に導入されたNISA制度の政策目的のひとつでもある「家計の安定的な資産形成」を、さらに推し進めていくために「令和5年度税制改正大綱」内で公開された新制度のことです。
新NISAは、非課税枠の大幅な拡大と保有期間の永久化が最大の特徴であり、1人あたり最大1,800万円までなら、投資で儲けた利益を非課税にするということになっています。
また、新NISAとともに、今人気になっているのが「分散投資」です。
全世界の株式に同時にできる「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」やアメリカの厳選された有名企業500銘柄と関連した「S&P 500」が人気であり、「リスクが少なくリターンが狙える」ということで人気を博しています。
Bloombergデータをもとに、SBI証券が作成した「米国株式 vs 全世界株式 長期パフォーマンス比較」によると、米国株式と全世界株式の累積年率は、それぞれ7.5%と5.9%となっています。
つまり、「教育投資」と同水準ということになりますね。
この点から、教育投資と新NISAとはバランスよく行った方が良いことが分かります。
リスクがあるとしたら、どんなに分散投資を行ったとしても、暴落のリスクを避けられないということです。
よくある誤解ですが、株式は年々一定に6%ずつ増えていくというものではありません。2008年には、-48.8%から-53.1%まで大きく下落しましたし、逆に2013年には1年で49.2%〜60.9%まで大きく上がりました。まるでジェットコースターのようです。
こうしたジェットコースターの波は、コツコツ投資していった結果の年率なので、長期保有しないと「リスクが少ないリターンが狙える」という状態にはなかなかなりません。
また、教育投資ならではの「子どもとのつながり」はありません。
老後に備えて、若いうちからコツコツ投資でためていく。そんなイメージになります。
教育投資と新NISA、どちらがおすすめかは価値観次第
このように、教育投資と新NISAでは、そもそも目的も受け取り方も大きく変わります。
将来、子どもの生涯賃金をあげて自由な生活をさせてあげたい。
そして、家族全体がより豊かになってほしい。
そんな目的で教育にお金をかけるのが教育投資です。
受け取る方ももちろん、子供が中心になります。
反面、新NISAでの「投資」は、長い目で見てコツコツ積み立てて、人生の後半戦を安定化させることが本来の目的であり、自分が受け取るのが主体です。
貴重な20代〜40代のお金。
あなたならどちらに投資をしますか?
これには正解はありません。
自分の価値観を見直して、どちらに投資するのか、そのバランスを見極めていただきたいと思います。
参照:
1.野村アセットマネジメント 資産運用研究所「投資信託に関する意識調査2024」
2.内閣府 男女共同参画局「平均値と最頻値考察~「平均初婚年齢」と「初婚年齢の最頻値」の間には3歳から4歳の差~」
3.令和4年 厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)
4.野村資本市場研究所「家計から見た教育投資の価値」
5.SBI証券「S&P500 vs オール・カントリー 2023年を考える」)
6.日本学生支援機構 平成 30 年度 学生生活調査結果



-150x112.png)


-150x112.png)



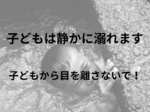



に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)



-300x169.jpg)