- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 【医師の論文解説】小児・青年期の医用画像による被曝と血液がんリスクへの影響
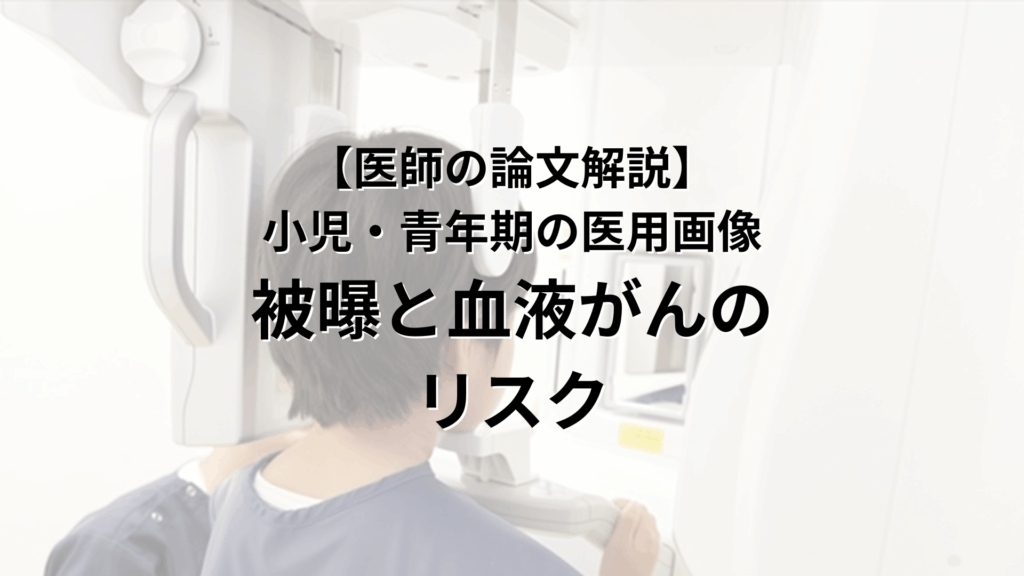
画像検査は、様々な病気を見つけ出して私たちの健康を守ります。医学的には極めて重要な検査で、病気を発見して治療することで多くの命を救っている検査です。一方で、「画像検査は被曝が心配だから子どもに受けさせるのは・・・」という声も聞こえてきます。成長期にある子どもから思春期の時期は、細胞分裂が盛んなため放射線の影響を受けやすく、成人よりも将来の発癌リスクが高くなる可能性があります。
そのようなこともあり、医療現場では不要な検査を避けたり、被曝量を最小に抑える努力を行っています。
今回は、医療目的の放射線を伴う画像検査が子どもや思春期の血液や骨髄、リンパ系の癌の発症にどの程度関係しているのかを検証した研究を紹介します。
論文
米国・カリフォルニア大学のRebecca Smith-Bindman氏らによるNEJM誌2025年10月の報告です。
研究の背景と目的:21歳までの子どもや若者を対象に、医療画像による放射線被曝量と血液癌の発症との関連を調査
これまで、子どものCT検査と白血病や脳腫瘍の発症リスクを結びつける報告はありましたが、それらの研究の多くは、対象人数が少なかったり、放射線被曝量を正確に評価できていませんでした。また、X線や核医学検査といったCT以外の画像検査を含めて、総合的に検討したような大規模な研究はほとんどありませんでした。
医療の現場では、救急診療や慢性疾患の経過観察など、子どもでも複数回の画像検査を受ける機会が増えています。そのため、累積の放射線被曝量と癌の発症リスクの関係を正確に評価することで、子どもに安全な医療を提供することにつながります。
この研究の目的は、出生から21歳までの子どもや若者を対象に、医療画像による放射線被曝量と血液癌の発症との関連を明らかにすることです。
研究の方法:1996年から2016年の間に出生し、21歳に達するまで追跡された約372万人が対象
この研究は、アメリカの6つの医療システムとカナダのオンタリオ州のデータを用いて行われました。
1996年から2016年の間に出生し、21歳に達するまで追跡された約372万人が対象となりました。それぞれの子どもについて、受けた医療画像検査の種類と回数を調べ、CTスキャン、X線、フルオロスコピー、核医学検査などによる被曝量を骨髄に届く放射線量としてミリグレイ(mGy)単位で推定しました。平均の追跡期間は約10年で、少なくとも6ヶ月以降に発症した血液や、骨髄、リンパ系の癌を解析対象としました。癌の発症情報は、医療記録と癌登録データを用いて確認されました。
統計解析では、被曝量がゼロの群と比較して、累積被曝量ごとの癌発症リスクを比較し、被曝量の増加とリスク上昇の関係を評価しました。
また、医療画像による放射線被曝が全体の癌発症のうち、どれほど説明できるか(寄与危険率)も推計しました。
研究の結果:放射線被曝量が高いほどがん発症リスクは上昇
研究の結果、被験者のうち2,961人が血液・骨髄・リンパ系腫瘍を発症しました。内訳は、リンパ系腫瘍が約80%、白血病などの骨髄性腫瘍が約15%、その他の稀な癌が約4%でした。
放射線被曝量と癌の発生リスクの間には明確な関連が認められ、被曝量が高いほど発症リスクは上昇していました。
累積被曝量が、15〜30mGy(頭部CTで1〜2回分に相当)ではリスクが1.8倍に、50〜100mGyでは約⒊6倍に上昇しました。
21歳までに血液がんを発症する確率は、被曝量30mGy以上では、1万人あたり25人程度、50mGyを超えると、40人程度と推定されました。
研究全体として医療画像による放射線被曝が原因と考えられる癌は、血液癌全体の10%程度と推定されました。
特に、CTスキャンによる被曝はリスクを上昇させ、頭部CTを受けた子ども血液がんのうち、4分の1程度が放射線に起因している可能性があると推定されました。
一方で、胸部X線などの被曝量が少ない検査のリスクは非常に小さく、統計的に有意なリスク上昇は見られませんでした。
研究から得られた知見:不要な放射線被曝を伴う検査は避けるべき
この研究では、医療画像による放射線被曝が子どもや思春期の若者の血液癌リスクを高めることについて、これまでで最も大規模なデータで示しました。
このデータからは、やはり不要な放射線被曝を伴う検査は避けるべきであるということは、間違いないでしょう。
しかし、医療被曝があれば必ず癌になるというわけではなく、医療被曝でリスクが上がるとはいうものの、CTを受けた人のなかで癌になる人が非常に少ないことも、この研究では示されています。被験者372万人のなかで癌になったのは2,961人で、割合にすると0.0008%と非常に低率なのです。被曝を恐れるあまりに必要な検査を受けないと、消化器の病気を見逃したり、診断がついたとしても治療方針が分からずに、命に関わる状況になったりと、被曝による癌のリスクをはるかに凌駕するリスクを背負いかねないのです。
小児科医の視点から
この研究から、医療者は放射線被曝を伴う検査を安易に行うのではなく、それが本当に必要なのかをしっかりと確認すること、放射線被曝を伴わない検査で代用できないかを十分に検討すること、検査の必要性を患者やその家族に十分説明することが重要であるということが分かりました。
検査は、実施すると思わぬ結果を見出すこともあり、「医師や家族が安心するためになされる検査」も少なからずあります。それは小児科医として、決してあってはならないことです。小児科医として、検査は必要性があって、どのような結果を予想して診断もしくは治療によってのみなされるべきだと、私は上級医から返し繰り返し学びました。そして、その考えは正しいと、この研究からも明らかにされました。
すなわち、患者やその家族としては、医療用の画像検査は確かに癌のリスクを高めるため、乱用は良くないが、むやみに避けるのではなく、必要性を認識したうえで実施すると、発癌リスクをはるかに超えるメリットがある検査ということは、知っておく必要があるでしょう。





とは?-子ども時代の体験が-大人になったときの-心と体に影響-150x112.jpg)



-150x112.png)






-280x210.png)

-300x169.jpg)