- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 「ギフテッド」を知っていますか?取り組みが遅れている日本の教育問題
-1024x576.png)
みなさんは「ギフテッド」という言葉をご存知ですか?
ギフテッドとは「並外れた才能を持つ子どもたち」のことをいいます。
知的能力ばかりではなく、特定の学問や芸術性、創造性、言語能力、リーダーシップなど、多岐にわたる分野で優れた才能を持つ子どもたちです。
何の才能もないと感じている人からしたら、羨ましいですよね。しかし、ギフテッドの才能は、時に理解されず、適切な支援を受けられないどころか、軽んじられることすらあります。
そこで、文部科学省も取り組みを始めたのがギフテッド教育です。
しかし、日本における理解と支援は、諸外国に比べまだまだ遅れているのが現状です。
今回、そんなギフテッドに焦点をあてて、ギフテッドによくありがちな「誤解」から、日本での取り組み、今後どう彼らを支援していけば良いのかまで深掘りしていきます。
ギフテッドとは?
ギフテッドとは、ある分野で飛び抜けた才能や秘めた可能性を持っている子どもたちのことです。
例えば、
- 難しいパズルをあっという間に解いてしまう
- 友達とのトラブルをみんなが納得する形で解決できる
- 誰も思いつかないような面白い物語を創作する
- ピアノを初めて数ヶ月で難しい曲を弾きこなす
- 運動会で誰よりも速く走る
こんな風に、何か一つ、あるいは、いくつもの分野で「すごい!」と思わせる才能や可能性を持った子どもたちが「ギフテッド」と呼ばれます。
ただ、才能が開花していなくても、秘めた可能性を秘めている子どもたちも、ギフテッドに含まれます。もしかしたら、今はクラスで目立たない子が、将来素晴らしい発明をするかもしれない。そんな可能性を秘めた子どもたちもギフテッドなのです。
この定義は、1972年にアメリカの教育省が出した「マーランド・レポート」という報告書に基づいています。このレポートは、ギフテッドへの理解を深め、彼らへの教育支援の必要性を訴える画期的なものでした。以来、このレポートの定義は世界中で広く受け入れられ、ギフテッド教育の基礎となっています。
ただ、才能があるかどうかを見分けるのは簡単ではありません。専門家の先生たちが、色々な方法を使って、その子の才能を見極める必要があります。
大切なのは、ギフテッドは特別な存在ではなく、様々な個性を持つ子どもたちの一人だということです。彼らの才能を理解し、伸ばせるようにサポートすることが、私たち大人の役割といえますね。
ギフテッドに対する5つの誤解
さて、アメリカでは1970年代からギフテッドが注目されていたわけですが、近年になって、やっと日本でも注目されるようになりました。
一方で、まだ日本ではギフテッドの歴史が浅く、誤解や偏見も根強く残っています。特に、以下の5つに誤解があることが多いです。(もしかするとみなさんも誤解しているかもしれません)
誤解その1:ギフテッドは天才や神童である
メディアでは、ギフテッドが超人的な能力を持つ天才や神童として描かれることがありますが、これは誤解です。
ギフテッドは、特定の分野において、並外れた才能や潜在能力を持っている子どもたちであり、必ずしも天才的な能力を発揮するわけではありません。
誤解その2:ギフテッドは発達障害の一部である
ギフテッドと発達障害は全く異なる概念です。
一部のギフテッドは、発達障害を併せ持つ「2E(重複障害)」と呼ばれるケースもありますが、ギフテッドであることと発達障害があることは、イコールではありません。
誤解その3:ギフテッドの才能は障害に伴って現れる
サヴァン症候群など、一部の障害を持つ人が並外れた才能を発揮するケースがあることから、ギフテッドの才能は障害と関連付けられて語られることがあります。
しかし、ギフテッドの才能は、障害とは無関係です。
誤解その4:ギフテッドは全ての分野で優れている
ギフテッドは、特定の分野において並外れた才能を持つことが多く、必ずしも全ての分野で優れているわけではありません。得意な分野があれば、苦手な分野もあるのが普通です。
誤解その5:ギフテッドは特別な支援を必要としない
ギフテッドは、恵まれているから勝手に育つだろうと思われがちですが、そうではありません。むしろ、ギフテッドの子どもたちはその才能ゆえに、標準的な教育環境では、十分に能力を伸ばせない可能性があります。
そのため、適切な支援や配慮が必要となるケースも少なくありません。
みなさんも誤解していませんでしたか?
このようなギフテッドに対する誤解は、ギフテッドへの適切な支援を妨げ、彼らの才能を十分に開花させる機会を奪ってしまいます。
ギフテッドは、文字通り天から与えられた素晴らしい「才能」です。
だからこそ、ギフテッドを 正しく育てるための、正しい理解と環境が必要なのです。
日本における「ギフテッド」への取り組みは遅れている
ところが、日本におけるギフテッドへの取り組みは、欧米諸国と比較すると遅れていると言わざるを得ません。
文部科学省は、2021年から「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」を開催するなど、ようやく具体的な対策に乗り出しました。しかし、ギフテッドへの支援体制や教育プログラムの整備は始まったばかりです。
一方、ギフテッドに関する研究は、日本でも細々とではありますが、脈々と続けられてきました。
明治時代には、教育学者の乙竹岩造や医師の榊保三郎が、ギフテッドへの理解と教育的配慮の必要性を訴えました。
大正時代には、京都で「第二教室」と呼ばれるギフテッド教育の実験的な試みが行われ、その後の追跡研究にもつながっています。
昭和に入ると、大伴茂らによる大規模な調査研究や、戦時中の「科学組」と呼ばれる特別な教育プログラムも実施されました。
近年では、特別支援教育や科学教育などの分野で、ギフテッドの特性や支援に関する研究が進んでいます。また、海外のギフテッド教育プログラムを紹介する論文も多く発表されています。
しかし、日本独自のギフティッド教育プログラムの開発や、統計的な裏付けのある実証研究は、いまだ限られているのが現状です。
このように、日本のギフテッド教育は、ようやくスタートラインに立ったばかり。ギフテッドの才能を適切に見抜き、その才能を伸ばせる環境を提供するためには、さらなる研究と実践の積み重ねが必要です。
日本が世界をリードできる素地を作るためには、まず才能あふれる子どもたちが、その能力を最大限に発揮できる社会を目指すことが大切ではないでしょうか。
ギフテッドの支援は今後どうすればいい?
では、才能あふれるギフテッドを正しく導き、支援をしていくためには今後私たちはどのようにしていけば良いのでしょうか?
以下の4つに分けて考えてみましょう。
①ギフテッドの子供を早期に発見し適切な評価をする
まずはともあれ、子どもが「ギフテッド」かどうかを見極められないと、当然支援に結びつけられないですよね。ギフテッドの才能を早期に発見し、適切に評価することが重要です。
そのためには、教師や保護者へのギフテッドに関する研修をするのも大切。 ギフテッドの特徴や支援方法についての理解を深めなければ、ギフテッドを見つけられません。
さらに、専門家によるアセスメント体制の整備も重要です。学校や地域にギフテッド児の才能を評価できる専門家(心理士、特別支援教育コーディネーターなど)を配置出来れば理想ですが、人手不足の昨今ですから、まずは気軽にギフテッドかどうかを相談できる機関を作れると良いですね。
また、日常生活や学習場面での行動から、ギフテッドの可能性を見つけられるツールを開発していくことも課題になっていくでしょう。
②ギフテッドの子供たちに多様な学習機会を提供する
ギフテッドは一様ではありません。
学習ニーズは生徒にあわせて多様に幅広くなっていくことでしょう。ひとりひとりのニーズに応えるため、多様な学習機会を提供することも大切になってきます。
例えば、飛び級制度や習熟度別学習など、個々の学習ペースに合わせた学習機会を提供することも一つの手です。また、オンライン教材や遠隔授業を活用し、高度な内容や興味関心に合わせた学習機会を提供するなど、学校の外でも自由に学べる環境を作ることも考えられます。
また、 ギフテッドの学習意欲を高める、挑戦的な教材や探究的な学習課題を作ってあげるのも良いですね。
例えば、科学に興味を持つギフテッド児には、高度な実験キットやオンライン科学講座を提供することで、彼らの探究心を刺激し、才能を伸ばすことができます。
➂ギフテッドの子供に対する社会情緒面への支援
ギフテッドは、その特性ゆえに、周囲との関係に悩むことがあります。
自分が異質な存在だからこそ、周りから拒絶されることも多く、逆に「普通になりたい」と願うギフテッドの子供たちは多いです。非常にもったいないですよね。
そこで、学校や地域に、ギフテッドの相談に乗れるカウンセラーを配置したり、同じような悩みを持つギフテッド児同士が交流できる場を提供するなど、社会心理的なサポート体制を作るのも重要な支援となります。
④ギフテッドを受け持つ教師への支援
ギフテッドを正しく導くのは、通常よりも難しいことは想像にかたくありません。
だからこそ、ギフテッドへの支援と同様に、ギフテッドを受け持つ教師への支援も重要になってきます。
例えば、教師への研修機会の提供し ギフテッド児の特性や指導方法についての研修を定期的に実施したり、 教師がギフテッド児の指導について気軽に相談できる専門家ネットワークを構築したりして、教師がギフテッドに対して相談できずに孤立する状況を作らないことも大切になってきます。
また、ギフテッドへの効果的な指導方法や教材を、教師同士で共有できるプラットフォームを構築するのも良いですね。
ギフテッドへの支援は社会全体で協力する
このように「ギフテッドへの支援」と一言でいっても、いろいろ考えなければならないことがあるのが分かりますね。もちろん、どれも決して一朝一夕に実現できるものではありません。
しかし、ギフテッドの才能を伸ばし、彼らの自己実現をサポートするためには、社会全体で協力し、粘り強く支援を続けていくことが重要です。そのとき、彼らの才能は日本の未来を創造する”力”となるでしょう。
参考文献:
⻆谷 詩織. これからのギフティッド研究と実践の発展のために. 教育心理学年報 62 巻 (2023)



-150x112.png)






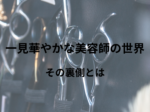







-300x169.jpg)