- Home
- コラム・インタビュー, 芸能・エンタメ
- 日本で唯一の国際女性映画祭「あいち国際女性映画祭」がもたらす映画の力

1996年に幕を開け、今年30回目を迎えた「あいち国際女性映画祭」は、現在、国内で唯一の「国際女性映画祭」として知られている(過去に開催されていた東京国際女性映画祭は2012年に終了)。
社会全体でジェンダーへの関心が高まる昨今、本映画祭の持つ意義や、映画を取り巻く社会はどのように変化してきているのだろうか。本映画祭のディレクターを務めるミニシアター・シネマスコーレ代表の木全純治氏と、名古屋国際工科専門職大学教授の佐藤久美氏、お二人にお話を伺った。
<目次>
「あいち国際女性映画祭」の特徴と意義
木全氏によれば、本映画祭の最大の特徴は、まず「女性監督の支援」にあるとのこと。さらに、脚本・音響・照明・メイク・カメラマンといった、“女性の映画の作り手”を支援する点に重きが置かれている。こうした女性映画人の活動を後押しする作品の選出こそが、「映画祭の主旨」なのだという。
開催地である「ウィルあいち」は、愛知県女性総合センターを正式名称とし、男女共同参画社会の拠点施設として設立。同映画祭も「女性支援のためのイベント」として始動した。
この映画祭は女性監督による作品であれば無条件に上映されるわけではなく、 “女性の生き方を描き、共感を呼ぶこと”が選定の明確な指針となっている。また男性監督による作品でも、この視点が色濃く反映されていれば選出することがある。しかしその割合は約1割程度にとどまるという。
国際女性映画祭の存在意義は、「いまの女性監督の力量を広く知ってもらい、女性監督作品の水準を社会に示す場」と木全氏は語る。

選定基準と記憶に残る作品
3つの選定基準
「女性の生き方」を描くという点以外にも、選定には以下の3つの基準がある。
| 1. エンターテインメントとしての魅力2. 社会問題を取り扱っていること3. 普遍的な価値観を持っていること |
木全氏の運営するシネマスコーレでは、アジアの社会問題を取り上げた映画が多く上映されているが、同氏は「まずは、映画作品としての『面白さ』が不可欠」と強調した。「社会問題に触れながら、エンタメ要素も両立できることが良質な映画の条件」との持論を語る。
印象深い作品の紹介
さらには30年の歴史の中で、両ディレクターが特に印象に残っている作品についても伺った。
「僕はこの映画をベルリン国際映画祭で見つけたんです。配給権は東宝東和が取得していましたが、先駆けて本映画祭でお披露目できました。上映時には会場を人の列が取り囲むほどの行列ができたことが、今も強く印象に残っています」
そう木全氏が迷わず挙げた映画は、1997年香港・日本合作の『宋家の三姉妹』だ。同作は1998年に国内のミニシアター系劇場で上映され話題となり、拡大上映・ロングランヒットを記録した。日本初上映は1997年のあいち国際女性映画祭である。この作品は映画祭の転機となるほどの反響を呼び、県外からも多くの観客が訪れるきっかけとなったという。

大学での教育テーマが「多文化共生社会」だという佐藤氏は、映画祭では国際交流企画を担当している。彼女は印象に残る1本として、2019年に日本・ミャンマー合作で難民問題を描いた『僕の帰る場所』を挙げる。
監督を務めた藤元明緒氏は、ミャンマー人の妻を持ち、難民や家族、アイデンティティの問題に深く踏み込んだ同作は高く評価された。藤元監督はその後、2025年には日仏ミャンマー・タイ共同制作の『LOST LAND』で、ヴェネツィア国際映画祭においてスタンディングオベーションを受け、三冠受賞という快挙を成し遂げている。
また映画祭では、毎回シンポジウムを開催している。2025年はポーランド・ウクライナ・フランス合作のドキュメンタリー『永遠の故郷ウクライナを逃れて』を上映後、ウクライナ問題に関するシンポジウムが開催され、非常に大きな反響を呼んだという。
映画が映し出す社会の変化
「映画祭がはじまって約30年の間に社会は大きく変化した」と佐藤氏。映画はその”変化”をどう描いているのだろうか?
マイノリティへの抵抗と理解

佐藤氏は「日本人監督の撮った、多様性、難民、マイノリティ視点に立った映画が増えている」と指摘する。そのひとつが、2022年に上映された日仏合作の『マイスモールランド』である。埼玉県在住のクルド人女子高校生を主人公に描いた同作は、カンヌ映画祭で日本人初の受賞を果たした。
同作で監督・脚本を務めた川和田恵真氏は、父親が英国人。さらに主演の嵐莉菜氏は、日本・ドイツ・イラン・イラク・ロシアの5カ国にルーツを持つ。ほぼ単一民族国家である日本において、多国籍のアイデンティティを持つ「マイノリティ」の立場から発信されるメッセージは、観る者の心に深く響く。
これに対し木全氏は、「日本ではマイノリティへの理解が乏しく、強い抵抗が起きている。それに対して、もっと映画や映画祭を通じて『相互理解』を発信していく時だと感じる」と話す。
映画がもつ力―異文化理解への道
移民や宗教といった現代社会の難題に対しても、「映画の力」は有効であると佐藤氏は語る。
「世界の約80億人の人口のうち、半数以上が何らかの宗教を信仰しているなかで、日本人は無宗教だと言われます。日本にはお盆とクリスマスのように異なる宗教的行事が共存する文化があり、それは日本のいいところでもあります。その一方で、宗教に対して根拠のない恐怖心を抱きがちです。映画は、異国の宗教や文化について、現地に行かずとも『共感』できる手段です」
共感し、身近に感じることこそが、「理解」へとつながる。これこそ、映画の大きな役割のひとつなのだろう。
映画祭の今後
30年を経て直面する課題
あいち国際女性映画祭がはじまった1996年。当時の日本における女性監督の割合は10%以下だった。現在は15%まで増えてはいるが、依然として少ない。
木全氏は「女性監督が増えない原因のひとつとして、女性のプロデューサーの少なさが挙げられる」と指摘する。プロデューサーは映画の企画立ち上げや予算、監督の起用という重要な役割を担う。女性プロデューサーは同じ女性監督に声をかけるケースが多いが、男性プロデューサーが女性監督に声をかけることは、まれだというのである。

一方佐藤氏は、「プロデューサーの性別だけではなく、女性監督作品へ投資するプロデューサー自体が少ないことが問題」と指摘。国の助成を受けて制作する映画や大手映画会社配給の映画で、女性監督作品の割合が1割に満たない現状を問題視している。

今後への希望
女性監督を取り囲む環境には依然として多くの課題が残されているが、映画祭には明るい兆しも見えているようだ。
実は、コンペティション部門の応募数は年々増加している傾向にあるという。そのようなこともあり、2024年からは新たにドキュメンタリー部門、アニメーション部門、ドラマ部門を設けた。2025年はおよそ650もの応募が集まったそうだ。
2025年上映の『長浜』を手掛けた谷口未央監督は3度目の参加である。「前2回のフィルムコンペティション受賞を経て初めての招待となり、この映画祭に育ててもらった」と記者会見で述べている。このような新しい才能を応援できていることこそ、本映画祭の大きな成果といえるだろう。
さらに本映画祭の直後、映画祭アンバサダーを務めた三島有紀子監督が、最新作『一月の声に歓びを刻め』がイタリア・トロペア映画祭で国際長編部門最優秀監督賞を受賞した。主演の前田敦子氏が国際長編部門最優秀主演女優賞を獲得したのもうれしい話題のひとつだ。

また、2025年は国内初上映(ジャパンプレミア)が7本、そのうち世界初上映(ワールドプレミア)が3本となった。「ワールドプレミアを実現できるのは映画祭にとって大変な名誉であり、貴重な機会」と木全氏は感慨深げに語る。
そして、この取材のわずか3日後には、2025年度のワールドプレミア作品のひとつである『金子文子 何が私をこうさせたか』がニューヨーク国際映画賞で長編映画部門最優秀監督賞(浜野佐知監督)、最優秀主演女優賞(菜葉菜)など、計5冠に輝いたというニュースが発表された。国内での公開は2026年2月を予定している。

次世代へ伝えたいこと
映画祭は「より良い未来」を目指す取り組みでもある。次世代を担う若者にとって、映画祭の果たす役割とは何だろうか。
佐藤氏は「戦争や紛争、女性の立場について、女性監督による“女性視点”で撮られることが重要」だと強調する。「戦争映画を男性が撮ると、戦場描写が中心となりがちですが、女性監督が撮ると、戦争の影で苦しむ家族の姿など別の側面が浮き彫りになります」とした。
一方木全氏は「映画との出会いが人生を変える契機となる」と語る。「10代20代の若いうちに出会った映画は強い印象を残します。若いときこそたくさんの映画、とくに社会と向き合う映画を多く観ることが重要」と、次世代への期待を寄せる。

木全純治氏プロフィール
愛知県出身。シネマスコーレ代表
1973年、同志社大学文学部卒業後、池袋の「文芸座」に入社し、日本映画を担当
1983年、映画監督・若松孝二氏の誘いを受けて、シネマスコーレの支配人に就任
当初は名画座として出発し、1986年から日本のインディペンデント映画や、中国、韓国、香港映画を上映。
2023年、シネマスコーレ開館40周年を機に坪井篤志氏に支配人の座を譲り、代表取締役に就任。40周年記念映画『青春ジャック 止められるか、俺たちを2』を制作
佐藤久美氏プロフィール
愛知県出身。名古屋国際工科専門職大学工科学部 教授
名古屋大学 大学院国際開発研究科 国際協力専攻 博士課程 修了。博士(学術)
名古屋を中心とする日本の伝統や歴史、文化などを紹介する英文情報誌『AVENUES』編集長・発行人を2009年まで約20年務める
2005年、「愛知万博フレンドシップ・フィルム・フェスティバル」(21か国の映画監督を招聘した映画製作事業)プロデューサー、金城学院大学国際情報学部 教授などを歴任したのち現職
NPO法人「愛知善意ガイドネットワーク」の理事長などのほか、国・地方自治体のまちづくりに関わる委員など幅広く活躍
(取材・文・写真 / 陽菜ひよ子)
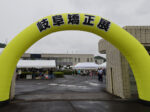


-150x112.png)
-150x112.png)
-150x112.png)
-150x112.png)
とは?あえて「集中しない」という選択肢」ライター:秋谷進(東京西徳洲会病院小児医療センター)-150x112.png)




-280x210.png)


-300x169.jpg)