- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 初期臨床研修医は平均年収435万円 研修医の平均年収と医師の働き方改革2024
初期臨床研修医は平均年収435万円 研修医の平均年収と医師の働き方改革2024
-1024x576.png)
最近、医師の働き方について注目が集まっているのをご存じですか?
医師の世界も2024年4月から厚生労働省による「働き方改革」が施行されました。
医師の「働き方改革」とは長時間労働で支えられていた医療機関に対して様々な「見直し」をしなければならないという制度です。
医師の長期間労働を規制し、医師がスムーズにキャリアアップできるための環境を整えようと、医療機関はさまざまな「工夫」をしなければいけなくなります。
特に注目されているのは「研修医」。
「勉強のため」「若いから苦労すべき」などという理由で、見合った仕事以上の仕事を医師に押し付けるという医療機関もありました。
それが「働き方改革」によって是正が行われるとすれば、研修医の働き方も変わってくると考えられます。
今回、そんな研修医にスポットをあてて、研修医の年収を実際の働き方と照らし合わせながら、その妥当性について検証していきましょう。
研修医とは?
そもそも研修医とはどんな職業かご存じですか?
一言でいうと「医師の見習い」のような立場の人達のことです。多くは最初の2年間を「研修医」とよびますね。
医師は各大学の医学部入学という難関を突破したのち、6年間かけて医師になるためのカリキュラムを学び、国家試験に合格すると医師免許をもらうことができます。
しかし5年生、6年生で臨床現場も垣間見るとはいえ、実務経験はほとんどなく「医師の世界」に飛び込むことになり・・・当然医師としての仕事が十分できるわけではありません。どの世界でも同じですよね。
そこで、医師の仕事を指導してもらいながら少しずつ覚え、研鑽していく期間を設けています。それが「研修医」です。
研修医にも前期と後期、「1年次と2年次」にわかれます。1年も現場の臨床に携わってくると、大きく成長します。そのため、給与も1年次と2年次で大きく変わってくることがほとんどです。
研修医の平均年収は?
では、そんな研修医の平均年収はどれくらいなのでしょうか?
厚生労働省が作成した「臨床病院における研修医の処遇」についての資料によると
臨床研修医の推定年収の平均は1年次で約435万円。2年次で481万円となっています。
また、臨床研修を受ける場所によっても異なっており、1年次で最大955万円、2年次で最大1,026万円もらっているケースがある一方で、最小は1年次で184万円、2年次でも184万円という結果です。かなりの格差ですよね。
ただ、さすがに900万円を超える給与というのは非常に稀であり、おおむね320万円から720万円の範囲内にあります。
そして、一般的に大学病院の方が給与が安いという傾向にあります。
大学病院で働いた場合、平均でみると1年次307万円、2年次で312万円となっています。
一方、臨床研修病院で働いた場合、平均で見ると1年次で451万円、2年次で502万円となっていますね。
| 大学病院 (114病院) | 臨床研修病院 (924病院) | 合計 (1038病院) | |
| 1年次 | |||
| 平均 | 3,074,172円 | 4,510,339円 | 4,352,610円 |
| 最大 | 4,239,600円 | 9,550,000円 | 9,550,000円 |
| 最小 | 1,842,000円 | 2,358,000円 | 1,842,000円 |
| 2年次 | |||
| 平均 | 3,123,132円 | 5,021,376円 | 4,812,899円 |
| 最大 | 4,560,000円 | 10,026,000円 | 10,260,000円 |
| 最小 | 1,842,000円 | 2,419,200円 | 1,842,000円 |
大学病院では全体の8割以上、臨床研修病院では9割以上で宿舎または住宅手当が用意されているのです。
ここまで書くと、「あれ?研修医は不当な扱いを受けていると言われる割には給料けっこうもらってるし優遇されている」と思いませんでしたか?
確かにその通りで、社会人になって1年目、2年目にしてはそこそこ良い給料ですよね。
実際、令和4年賃金構造基本統計調査によると、大卒者で入社してから1年目の賃金は月額22.8万円となっており、大学院生でも月額26.7万円となっています。一般的な日本の給与との比較はどうなのか。国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均年収は「458万」。研修医1年目2年目は決して「不当に安い給与」とは言えないわけです。
では、どうして研修医だけクローズアップされることが多いのか。それは年収だけでは割り切れない「労働時間」にあります。
| 当直回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~ | 合計 |
| 大学病院 | 18 | 2 | 7 | 6 | 55 | 24 | 3 | 0 | 115 |
| 臨床研修病院 | 11 | 13 | 90 | 156 | 459 | 98 | 44 | 35 | 906 |
参照:
厚生労働省「臨床病院における研修医の処遇」
厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
医師の高給は時間外労働でも支えられている
そもそも医師は時間外労働に追われやすい職業の一つ。
病気やケガはある日突然やってきます。
受け持っている患者さんがいつ急変するかもわかりません。
その時医療的な判断が迫られるのは医師であり、医師でないと出来ない処置はたくさんあります。
だからこそ、急な呼び出しや対応に追われることも必然的に多くなるのです。
実際、厚生労働省による医師全体の「勤務環境把握に関する研究」によると、時間外・休日労働時間が年960時間以上になっている割合は21.2%もいます。つまり5人に1人は月80時間以上も残業しているというわけです。
特に、脳神経外科や形成外科、外科や産婦人科といった急変しやすい科で時間外労働が見られています。
しかも、その矢面にたちやすいのが研修医。
通常、臨床現場では指導医だけが急変対応に追われるといったことはほとんどありません。
指導医が状況を把握しながら、研究医が実務を担当することが往々にしてあります。
つまり、経験を早く積んで一人前にならなければならない研修医は多くの時間外労働を強いられやすい環境にあるのです。
事実、当直回数も臨床研修も月4回が最多となっており、施設によっては月5回〜6回の施設も20%程度、月7回以上の施設もあるくらいです。
しかも、他の職種だと当直した翌日は休みになっているところがほとんどですが、研修医だけはそのまま日中も勤務しているということが「あたりまえ」になっています。
また研修医の場合、経験を積むことが一番の目的なので「仕事」と「教育」の境目が曖昧になりやすいのも特徴の一つ。
つまり実際は時間外労働なのにもかかわらず「自己研鑽」という意味合いで無給で働いている場面も出てきます。
専門医をとるためのレポート作成や論文作成、学会発表のための資料作り。
これらはみな、研修医が一人前になるための「自己研鑽」の時間と考えられてしまいます。
多くの施設では時間外労働とは認めていないでしょう。
このように考えてみると、先の研修医の年収は多くの夜勤、時間外労働、加えて自己研鑽の時間をもとに成り立っている年収です。
どうでしょう?
みなさんの目からは「妥当」に見えますか?
参照:
厚生労働省「第18回 医師の働き方改革の推進に関する検討会:医師の勤務実態について」
厚生労働省「臨床病院における研修医の処遇」
医師の働き方でどこまで研修医の生活が変わっていくのか?
さて、研修医を含めた医師の時間外労働が問題視され「医師の働き方改革」が2024年4月からスタートしました。
具体的には、病院などで働く医師の時間外労働の上限は、原則年960時間、月の平均で80時間にすることを前提として、勤務時間の短縮が求められるようになるのです。
しかし、医師の仕事が少なくなったわけではありません。弊害は出てこないのでしょうか。そうならないように、施設を「A水準」「B水準」「C水準」の3つに分けて管理されるようになります。
A水準は、ほとんどの病院が対象になっている働き方改革関連法に基づき2024年度以降適用される水準のこと。上限は原則年960時間です。ただし一部の医療機関では、年1,860時間を上限として、A水準を超える内容の36協定を結ぶことが可能となります。
B水準は地域医療提供体制の確保の観点から暫定的に設置している施設が対象になっている水準のこと。簡単にいうと、地域医療を支えるのに「やむなく」時間外労働が必要になりやすい施設ですね。3次救急病院や、救急車を年間1,000台以上受け入れる2次救急病院などが該当します。
B水準に指定された場合、年間残業時間は1860時間まで緩和されますが、他の健康確保措置などはA水準同様かより厳しく必須になります。特に「連続勤務時間28時間」「勤務間インターバル9時間」の確保が「努力義務」ではなく「義務」になるのは大きいですよね。
C水準は、研修等を行う施設に適用されます(集中的技能向上水準)。
C-1水準は臨床研修医・専攻医を対象とし、医師は自らプログラムを選択・応募します。
つまり、多くの研修医はこの「C-1水準」に該当する施設に従事することになりますね。
研修医・専攻医に対する時間外労働規制は全てC-1基準に該当するため、他のB水準を取得している病院であっても、C-1水準を取得しなければ研修医・専攻医を960時間以上働かせることはできません。
C-1水準を取得するには、プログラム募集時に時間外労働時間の上限を示す必要があったり、カリキュラムを組んでおかないといけないルールがあります。
すると、時間外労働の上限を多く見積もる施設は研修医に選ばれない可能性がでてくるので、自然と引き下げにかかるだろうと目算しているわけです。
このように、4月から研修医を含めた多くの勤務医で時間外労働が統制されるようになります。今後研修医がどのような生活に変わっていくのか、注目が集まります。
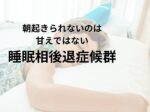



-150x112.png)

-150x112.png)

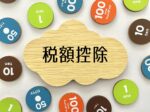
-150x112.png)




に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)
-280x210.png)
の看板-280x210.jpg)

-300x169.jpg)