- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 知られざる日本製OS「TRON(トロン)」の真実と「坂村健」氏の驚くべき成果について
知られざる日本製OS「TRON(トロン)」の真実と「坂村健」氏の驚くべき成果について
」の真実と「坂村健」氏の驚くべき成果について」ライター:秋谷進(東京西徳洲会病院小児医療センター)-1024x576.png)
突然ですが、みなさんはパソコンの操作やアプリなどを使うために必要なソフトウェア「OS(Operating System)」の代表例といえば、何を思い浮かべますか?
ほとんどの人がおそらく「Windows(ウィンドウズ)」「macOS(マックオーエス)」などを思い浮かべるのではないでしょうか。エンジニアのなかには「Unix(ユニックス) 」「Linux(リナックス)」をあげる方もいるかもしれませんね。
しかし、これらよりももっと地味でありながら、大きな世界的シェアを取っている日本製OSがあります。
それが「TRON(トロン)」と呼ばれる日本製OSです。
今回は、このTRONが作られた経緯から、あまり知られていないTRONの活用例、そしてTRONの作成者である「坂村健」氏について深堀りしていきます。
TRONとは何か? ~身近な製品で活躍する縁の下の力持ち~
TRONも 「さまざまな電子機器を動かすための基本ソフト(OS)」 の一種ですが、その最も大きな特徴は、家電製品、自動車、産業機器など、私たちの身の回りにある 多種多様な電子機器に組み込むことができる 点です。
例えば、皆さんが毎日使う電子レンジやエアコン、洗濯機といった家電製品にも、TRONが搭載されているかもしれません。また、自動車のエンジン制御やカーナビゲーションシステム、さらには工場の自動制御システムなど、普段意識することは少ないですが、社会の基盤を支える重要なシステムにもTRONは活用されています。
TRONは、パソコン向けのWindowsやmacOSのように目立つ存在ではありませんが、 縁の下の力持ちとして私たちの生活を支えている、非常に重要な役割を担っているのです。
TRONは 「オープンアーキテクチャ」 を採用しています。
これは、TRONの設計図を公開し、誰でも自由にその設計図に基づいてOSを作ったり、改良したりできるということです。例えるなら、おいしい料理のレシピを公開して、誰でもそのレシピを見て自由に料理を作ったり、アレンジを加えたりできるようなものです。
このオープンな仕組みのおかげで、TRONはさまざまな機器に対応し、幅広い分野で活躍することが可能となりました。特に、携帯電話やデジタルカメラなどの小型電子機器では、TRONが圧倒的なシェアを誇っています。TRONは、コンパクトで、リアルタイム処理を得意とし、省電力性に優れているという特徴があります。これらの特徴は、小型でバッテリー駆動の機器に最適であり、TRONが組み込みシステムの世界で広く採用されている理由となっています。
実際、2024年4月にトロンフォーラムで発表された「2023年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査報告書」によると、組込みシステムに組み込んだOSのAPIでTRON系OSが約60%のシェアを達成し、25回連続の利用実績トップとなっています。
このようにTRONは、普段目にする機会は少ないかもしれませんが、実は世界中で非常に多くの機器に搭載され、私たちの生活を陰ながら支えている、非常に重要なOSなのです。
参照:トロンフォーラム「組込みシステムに組み込んだOSのAPIでTRON系OSが約60%のシェアを達成し25回連続の利用実績トップ」
TRONの生みの親、坂村健 ~コンピュータの未来を拓く先駆者~
TRONを生み出したのは、東京大学名誉教授の坂村健氏です。
1951年東京生まれの坂村氏は、日本のコンピュータ科学界を代表する研究者の一人であり、オープンアーキテクチャに基づくTRONの開発を通じて、コンピュータ技術の新たな可能性を切り拓いてきました。
坂村氏の構想は、「どこでもコンピュータ」という理想的なコンピュータ環境の実現です。これは、私たちの身の回りのあらゆる場所にコンピュータが組み込まれた機器が存在し、それらがネットワークで繋がることで、人々の生活をより豊かに、便利にするという未来像です。TRONはこの理念を具現化するために開発され、家電製品から自動車、産業機器まで、多種多様な電子機器に搭載可能なOSとして設計されました。
坂村氏のTRON開発におけるリーダーシップと先見性は、世界中で高く評価されています。TRONは現在、IEEE(アイ・トリプル・イー)標準の組み込みOSとして、世界中の無数の機器に搭載されています。IEEEとは、電気・電子・情報・通信分野における世界最大の学会のこと。TRONがIEEE標準に採用されたことは、その技術的な信頼性と革新性を裏付けるものである、ということになります。
2015年には、情報通信技術の発展に貢献した世界の6人の1人として、ITU(国際電気通信連合)150周年記念賞を受賞。さらに2023年には、IEEE Masaru Ibuka Consumer Technology Awardを受賞するなど、その功績は国際的に認められています。
また、IoT 時代の新しい学び舎として、2017 年 4 月に東洋大学情報連携学部(INIAD)を開設し、IoT連携を身につけるための空間と,先進的な IoT 環境を備えた INIAD Hub-1 という校舎を新たに建て、コンピュータ・サイエンスの教育や、様々なプロジェクトのフィールドを作り上げてきました。
このように、坂村氏は、研究者としての活動に加え、著書を通じて技術の普及やイノベーションの促進にも力を注いでいます。『DXとは何か』『IoTとは何か』など、技術の未来を分かりやすく解説した書籍を多数出版し、技術者だけでなく一般の人々にもコンピュータ技術への理解を深める機会を提供しているのです。
TRONの開発と普及、そして技術を通じた社会貢献への熱意。
坂村健氏は、まさに日本のコンピュータ技術の未来を拓く先駆者といえるでしょう。
TRONが切り拓いた未来、そして今後の展望
TRONは、私たちの生活を支える多くの電子機器に搭載され、その活躍の場はますます広がっています。特にIoT(Internet of Things、モノのインターネット)の普及により、TRONは家電製品、自動車、産業機器など、あらゆるモノをネットワークで繋ぎ、よりスマートで便利な社会を実現する上で、欠かせない存在となっています。
例えば、TRONを搭載したスマート家電は、スマートフォンから遠隔操作したり、音声アシスタントと連携して操作したりすることが可能です。また、TRONを搭載した自動車は、リアルタイムの交通情報や車両の状態を収集・分析し、安全運転や効率的な運転を支援します。さらに、TRONを搭載した工場では、生産ラインの自動化や遠隔監視を実現し、生産性の向上やコスト削減に貢献しています。
さらに、TRONは、オープンアーキテクチャという特徴を生かし、今後も様々な分野での応用が期待されています。特に、AI(人工知能)やロボット技術との連携は、TRONの新たな可能性を切り拓くでしょう。例えば、TRONを搭載したロボットは、AIによる高度な判断能力とTRONのリアルタイム処理能力を組み合わせることで、より複雑な作業やサービスを提供することが可能になるでしょう。
それだけではありません。TRONは、エネルギー効率の向上や環境負荷の低減にも貢献できます。TRONの省電力性は、バッテリー駆動の機器の動作時間を延長し、充電回数を減らすことで、エネルギー消費を抑えることができるのが、最大の特徴の一つ。そして、TRONを搭載した機器は、ネットワークを通じてエネルギー使用状況を監視・制御することで、無駄なエネルギー消費を削減し、環境負荷を低減することができます。
このように、TRONは、坂村健氏の「どこでもコンピュータ」という理念のもと、着実に進化を続けています。TRONは、今後もIoT、AI、ロボット技術などの発展とともに、私たちの生活をより豊かに、便利にするための基盤技術として、ますます重要な役割を担っていくでしょう。
TRONは、私たち日本にとって、大切な国産テクノロジーの一つです。なかなか目の触れることのない「影のテクノロジー」ではありますが、見かけたらぜひ応援していきたいですね。
参照:
1.INIAD:IoT 時代の新しい学び舎. 別所 正博,坂村 健. 情報の科学と技術 67 巻 11 号,582~588(2017)
2.K. Sakamura. The TRON Project. IEEE Micro, vol.7, no.2,pp.8-14, 1987
3.TRON Real-time OS Family Honored as an IEEE Milestone



-150x112.png)




-150x112.png)

-150x112.png)

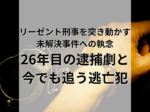
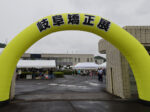

-280x210.png)


-300x169.jpg)