- Home
- ライティングコンテスト
- 小児科医が考える生成AIと未来
小児科医が考える生成AIと未来
- 2024/2/26
- ライティングコンテスト
- 佳作, 第4回ライティングコンテスト
- コメントを書く
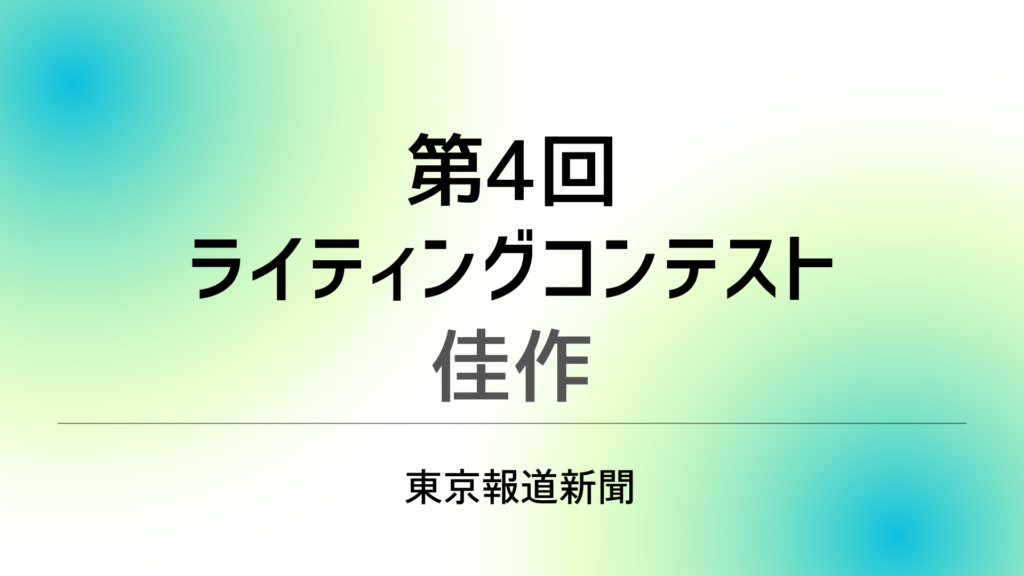
生成AIによって明るい未来と、それと相反する先の見えない未来が見えている。小児科医としても同じことがいえる。まずはAIによる恩恵の部分から話そう。
日本の医療制度では、どの医師が診療しても診療報酬は同じだ。すなわちスーパードクターが診療しても、研修医が診療しても病院の収益は一緒ということになる。
患者の側からすれば、できれば名医にかかりたい。がんなどの大病を見過ごされれば、たとえ医師から謝罪があったとしても無意味といっても過言ではない。見過ごされた結果、死に至れば、死んだ本人もその家族も無念しか残らないだろう。だがAIがあれば、画像診断において支援をしてくれる。これまでのデータ、内視鏡検査、レントゲン、頭部CTや頭部MRIといった画像から判断し、AIが病変を見抜いてくれる未来が訪れる。これはAIにしかできないことだろう。人間の目であれば、どんなベテランでも見逃しはある。しかしAIに見逃しはない。
なんと明るい未来だろうか。その未来に向けて、実はもう動き出している。実は画像診断の診療報酬は引き下げられているのだから。医師不足の解消にもなるのだが、画像診断は医師ではなくAIに任せるように、業界が動き始めているということだ。しかしその反面、画像診断における医師の技量が落ちることは間違いないだろう。診療報酬が少ないのであれば、自分で行う医師は減るだろうし、病院側もさせないとなると、医師が画像診断をする機会が減るのだから当然のことだ。AI診断により学ぶことも多いが、自らを研鑽して画像診断を学ぼうとする医師は減少するだろうし、もしかすると画像診断ができない医師が増えることにも繋がるかもしれない。求められていない場所に、人はいけないのだから仕方がない。
また、受付の問診票や血圧の管理なども、すでにAIが導入されている。問診をAIに任せることで、どの科に受診すればいいのかが割り振られるのである。医療従事者の負担も減るし、患者も余計な質問をするなどの手間も省けるそうだ。しかし、これらの進歩において人と人との関わりが薄れるのではないかと、私は危惧している。
「こうこうこういうことで困っています」
「えー。そんなに大変なんですね」
「そうなんですよ」
といったニュアンスなどを読み取ることはAIにはできないだろうし、医療従事者側もそういったことを学んだりする機会が失われる。人の意志は言葉にできない部分にもあると、私は考えているので、空気の読めない医師が増えるのは問題だとも感じている。
ここで例え話をしよう。医療とは関係はないが、例えば誰かとつきあいたいと思えば、今はマッチングアプリを利用すればいい。私自身が使ったことがないので、どういった駆け引きがあるのかは分からないが、ボタンを押せば簡単に恋人ができる仕組みになっているのだと思う。
私が若い頃は、ちょっと伝えたことがあるけれども、本人の前では言えない。でも伝えたい。じゃあ手紙にしようか電話にしようか。と、悩みながら、それでも勇気を持って行動し、ようやく大好きな人と出会い、恋人になった。そんな困難があるからこそ、達成感があるのではないだろうか。それが、今はない。その楽しみを奪ったのは便利さを求めた大人たちだ。
しかし、スマートフォンが、ただの電話ではなく進化したように、今ではインターネットなしでは生きていけない。何をするにしても、インターネットが基準の世の中になってしまっているからだ。
コロナ禍において人と人との関わりが減ったことで幼児たちの発達が遅れていることがわかった。つまり、人は人との関わりによって、発達していくということだ。対話というのは、ただの言語ではなく、人が人らしく生きていくために必要なものと言える。
しかし、現在は人との関りが減少していく方向へと進んでいる。仕事だってそうだ。誰にも相談せずに生成AIの技術によって仕事を進めることできる。だが一人の人間の限界など高が知れている。それで本当に次の時代を作っていけるのだろうか。
TVで芸能人を模した生成AIのロボットを見た。確かに数年前からすればあり得ないほどの進歩だ。きっとTVで見るロボットのもとになっている芸能人はこう言うだろうと思う反面、この芸能人はきっとこうは言わないだろうという違和感も覚えた。ロボットは所詮ロボットだ。ただ、生成AIが進歩すればこの違和感はなくなるかもしれない。それと同時に、我々のコミュニケーション能力も低下して、違和感すら覚えなくなるかもしれない。
子ども診療をしている小児科医としては、生成AIによる恩恵は多大なものと考える。生成AIの人への影響は大きい。しかし影響が大きい分、人の様々な能力の低下……特に子どもの能力の低下を、私は危惧している。
ライター:秋谷 進
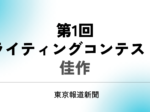
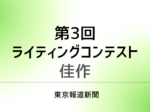
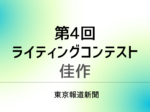
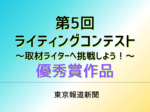

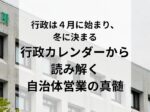






-300x169.jpg)