- Home
- ライティングコンテスト
- 体と脳
体と脳
- 2024/2/24
- ライティングコンテスト
- 佳作, 第4回ライティングコンテスト
- コメントを書く
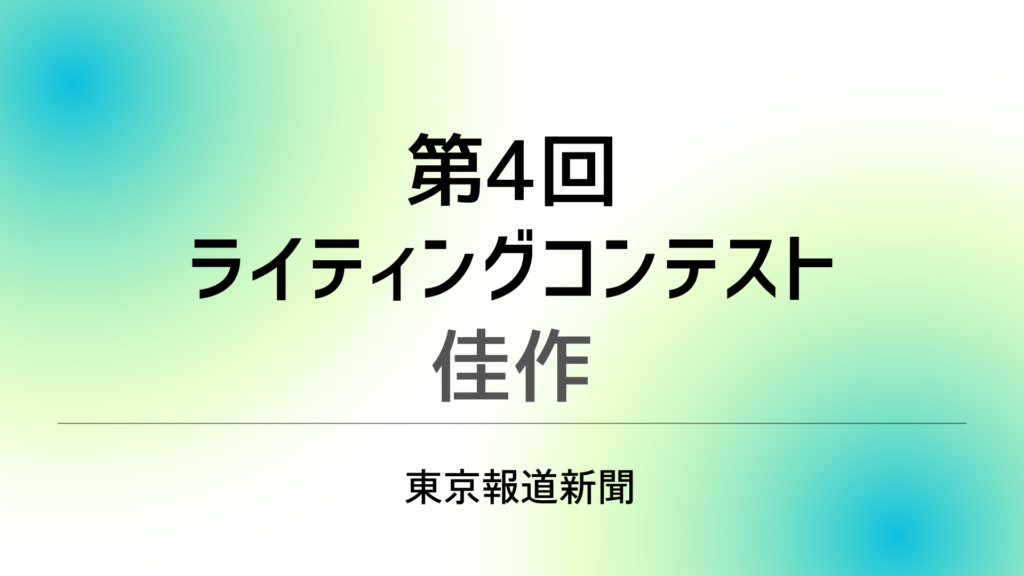
「東京同情塔」で第170回芥川賞を受賞した九段理江さんが受賞記者会見で「5%ぐらい生成AIの文章を使っている」と発言したことを受けて文芸の世界でも人とAIとの協働が進んでいるという印象を強くした。
哲学者であり作家でもある千葉雅也さんも自身のXなどでAIの活用に前向きな意見を発言しており、人とAIは決して敵対的な関係にあるのではなく、AIをいかに有効に活用するかと考えることが重要なのだろう。
例えば家事労働などの分野で様々な機器が開発されたことにより家事労働にかかる時間は大幅に短縮された。冷蔵庫、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機など今の私たちの生活に欠かせないこれらの機械に対して人の仕事を奪うからけしからんと言う人はほとんどいないだろう。
しかし、機械化により生み出された余暇をどう使うかは個々人の判断に委ねられる。無意識の間にスマホ記事に惹きつけられオススメされる記事に没入して時間を浪費してしまうなら余暇を有効に活用出来ているとは言えないかもしれない。
そうならないためにも、自分が生きたいと思う人生を生きるために有限の時間を使っているのだと意識することが大事だろう。自分が生きたい人生とは何かを考えることはAIにはない人間の特質とは何かを考えることと繋がる。ギリシア時代以来多くの哲学者が人とはどんな生き物なのかという問いを繰り返し問い続けてきた。あなたはその問いにどう答えるだろうか?
一般に良く言われるのは介護や看護などのケアに関わる仕事は心を持つ人間が得意な分野だと言われる。
医療分野で赤ちゃんを模したロボットが何も出来ず助けてもらわなければならないがゆえに、関わる人たちのお世話をしたいという欲求を満たし、その人たちの自己肯定感を高める効果があるという研究結果が発表された。そのニュースを聞いて私は人間の複雑なあり方に興味を惹かれた。
従来の発想では、弱った人には強いサポートが必要だと考えられてきた。障がい者には介護者が付き添い、老人ホームでは若いスタッフがケアをする。子ども達は大人が正しい方向へと教え導いていく。
赤ちゃんロボットの例からは、弱っている人は自分よりもさらに弱い存在を世話することにより、自らの活力が引き出されるということが明らかになった。高齢者が子育て卒業後や退職後に犬を飼い、犬を世話することで生きがいを感じるということも同様の心理を背景にしているのかもしれない。子育てをしていると、子どもに時間を取られているような気がしてしまう。そんな魔がさす瞬間があるが、人を世話することを通して自らの人生に張りを感じているという面もあるのかもしれない。
話は変わるが、解剖学者の養老孟司さんの「バカの壁」という本が以前ベストセラーになったが、そこでは脳化社会の脆弱性について語られていた。体よりも脳を優先するあまり体で考えたらおかしいとわかることが脳の判断によれば正しいとされてしまい様々な齟齬が生じているという話だった。
例えば、兵器の進化を考えてみる。人類にとって最も原始的な武器は刃物だった。石を削って斧を作ってマンモスの肉を獲得するために活用した。人間同士の争いについても近代までは刀や弓矢、槍などを使って戦争をしていた。しかし近世になり火薬の発明に伴い銃が使用されるようになると戦争が劇的に変化する。日本でも織田信長が火縄銃を活用して戦争に革新をもたらした。兵器が刀から銃に移行することにより戦争はどう変化したか?自らの体と敵の体との間に距離が生じることになった。その距離は殺傷や殺人の際に体が感じる様々な感触を遠ざけることにつながる。
例えば敵の肉を断つ感触や返り血を浴びる感触など様々な不快感を感じずに済むということである。戦争における痛みを感じる機会の喪失は銃器の使用に始まり、地雷の使用や原爆投下などの行為に繋がっていく。湾岸戦争以来のまるで現実の世界があたかもテレビゲームで起こっているフィクションに近いものとして感じられるという現象は銃器の脱体感という特質に発するものだ。戦争の効率化という観点で言えば、銃器の発明は画期的な進化だっただろう。
しかし、それをきっかけにして人類は原爆や水爆という人類を滅亡させる危険を孕む兵器を手にしもはや後戻りすることは出来ない地点まできてしまった。核兵器に対する恐怖心を緩和するために自国でも核兵器を持ちお互いに抑止し合うという核抑止の考え方により、地球上には数多くの核兵器が配備されることとなった。
この例は脳化の危険性を示す大きな一例だろう。ここから考えられる教訓は体が持つ力を大事に考えるということだ。
AIと人間の関係を思い切って脳と体と考えてみても良いかもしれない。AIという脳はとても優秀だ。AIは膨大の情報を一瞬で処理することが出来る。人間が忘れてしまうような事もAIは記憶を保持し続けることができる。そうした力をものさしにすれば人間はAIには敵わない。
しかし、一方で人間は体や心というAIが持ち得ないものを持っている。不快という感覚を元にして脳の働きに歯止めをかけることも体の重要な役割の一つである。AIの利点を十分に活用しつつも、手綱を握っているのは人間であるという意識を持ってAIと前向きな関係を築いていくことが出来ればAIの進化はこれまでにない新しいものを生み出すチャンスとなるだろう。
ライター:貴田雄介

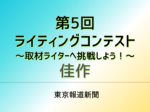
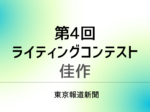







-300x169.jpg)