- Home
- ライティングコンテスト
- AIが脇役の世界 ~建設産業界の若手不足とAIがもたらすもの~
AIが脇役の世界 ~建設産業界の若手不足とAIがもたらすもの~
- 2024/2/27
- ライティングコンテスト
- 東京報道新聞賞, 第4回ライティングコンテスト
- コメントを書く
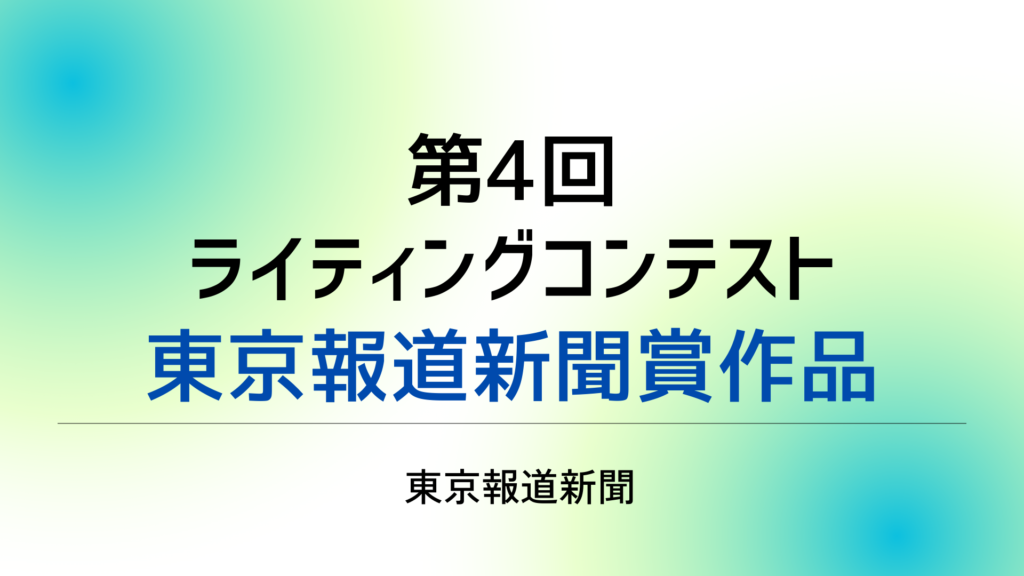
AI技術の進歩とともに、AIに取って代わられない職業とは何かということが考えられるようになった。そのような問いは、実際に職業選択の際にも大きな影響を及ぼしている。そんな中で、私は建設技術者という職業はAIに取って代わられず、今後注目に値する職業だと考えている。そこにはマニュアル化しにくいという建設業界ならではの特性が作用している。建設産業界で重要なことは、AIに取って代わることができない技術者の直観なのである。
残念なことにAIが取って代わることができない職にもかかわらず、建設産業界の若手不足は年々進行していく。国土交通省(2023)の調査によると、業界全体人口の約4割が55歳以上で29歳以下はわずか1割に留まっている。このような状況下で、多くの企業は「どのように若手を確保するか」という量の問いに頭を悩まされている。
他方、若手が少ない中で「どのように技術を継承するか」という質の問題も同時に生じている。この後者の問題に関しては、すぐには結果がでにくいことから後回しにされがちだ。しかし、この後者の質の問題解決に取り組むことで、量の問題解決の糸口が見えてくる。
常に量と質は表裏一体の関係にある。建設産業界も同様であろう。下の図が示すのは、建設産業界における質と量の問題とその循環関係を示している。技術継承という問題が解決されたとき、建設技術の高度化、効率化が起こり、結果的に働き方という面で建設産業界の新しい良いイメージが構築できるかもしれない。
そういった良いイメージは、若手の職業選択に影響を与え、若手人口の増加につながるであろう。もし若手人口が増えれば、今度は技術継承をする母体数も増加する。実際、建設産業界を若手が志望しなくなっている大きな理由は長時間労働という悪いイメージによるものだ。量の問題に取り組むこと自体が間違いではないが、量の問題と同様に質の問題にも尽力する必要があり、このサイクルを生み出すことが求められるのである。
AIが脇役の世界-1024x575.png)
建設技術者の直観はAIに取って代わられないが、その直観の継承に拍車をかけるのはAIである。そもそも建設技術者の直観とは、積み重ねてきた知識や知恵,経験から発揮される能力が何であるかを特定することだ(山﨑2020)。その能力の可視化、共有という点は、まさにAIが得意としている領域のように思える。たとえば、AIを用いることによって、若手は先輩技術者から学んだコツやノウハウを仮想空間で実行することができるかもしれない。
建設産業界におけるミスは、命にも関わる大きな事故につながる。ミスが許されないからこそ、若手の裁量権は狭まってしまっているのが現実だ。そこにAIというツールが、ミスが許される環境を創り出すことによって若手は事前にシミュレーションすることができる。その結果、若手の裁量権はさらに広がり、それはやりがいにもつながるだろう。そういったやりがいも先ほどのサイクルを生み出すうえで重要な要素である。
近年では、建設産業界においてOff-JT教育の重要性が強調されるようになった(小野2021)。Off-JT教育とは、技術者たちがマニュアルに則って1から学習を進めるのではなく、必要なときに必要な情報をピックアップして研修を受けるという能動的な学習スタイルである。建設産業界とOff-JT教育は非常に相性が良いが、実施する人材の確保という難点から、企業規模ごとに大きな差が出てしまっている。実際、企業の従業員数が少なくなるにつれて、Off-JT教育の実施割合が下がっていることが調査の結果わかっている(荒川2021)。
AIの活用は、業界におけるOff-JT教育の均一化という問題にも取り組めると私は考えている。たとえば、AIの技術を使えば、ノウハウを持った技術者はそのノウハウを動画やテキストにしてアプリケーション上で共有することができる。そのようなアプリケーションで、若手技術者たちは、自社にとどまらず全国にいる自分が必要なノウハウを持つ技術者をそこで探すことができ、さらに前述した仮想空間などを用いればミスが可能な空間での応用も可能だ。
理想論ではあるが、これを叶えるためには、まず業界全体で協調する領域と競争する領域を明確に分けることが欠かせない。どの建設技術者も自分の技術をもって、日本、世界を創り上げ、支えていきたいという共通の想いを持っているであろう。一度その共通の想いに立ち返って、この「どのように技術を継承するか」という質の問題に関しては、協調領域として扱うことが求められる。
ただ、「若手をどのように確保するか」という量の問題は競争領域であるべきであろう。それは会社によって強みや重点領域は異なり、結果的に確保したい人材も異なるからである。このように今後の建設産業界の人材問題には、協調・競争領域を分けたうえで、AIを導入することが求められる。AIは建設産業界における主役にはなりえない。ただ、その主役候補を実際に主役にするのはAIなのかもしれないのである。
参考文献
荒川創太(独立行政法人労働政策研究・研修機構・調査部)(2021). 「職場における能力開発の現状と課題 ~JILPTの最新調査結果から」. 労働政策フォーラム「これからの能力開発・キャリア形成を考える」にて発表.
小野貴史(2021).「建設業における人財育成教育 「Off-JT」の必要性 〜一般社団法人北陸建設アカデミーの取り組みと課題〜」.『建設マネジメント技術』, 1月号, pp.44-50.
経済産業省(2015).『2015年版ものづくり白書』.
国土交通省不動産・建設経済局(2023).『最近の建設業を巡る状況について【報告】』.
山﨑雅夫(2020). 『技術者直観形成論 ―理論と実践―』. 法政大学出版.
ライター:皆川翔
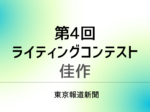

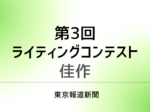
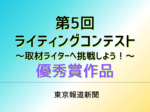
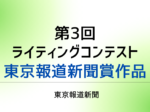







-300x169.jpg)