- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- これでいいのか?動き始めた日本の新専門医制度
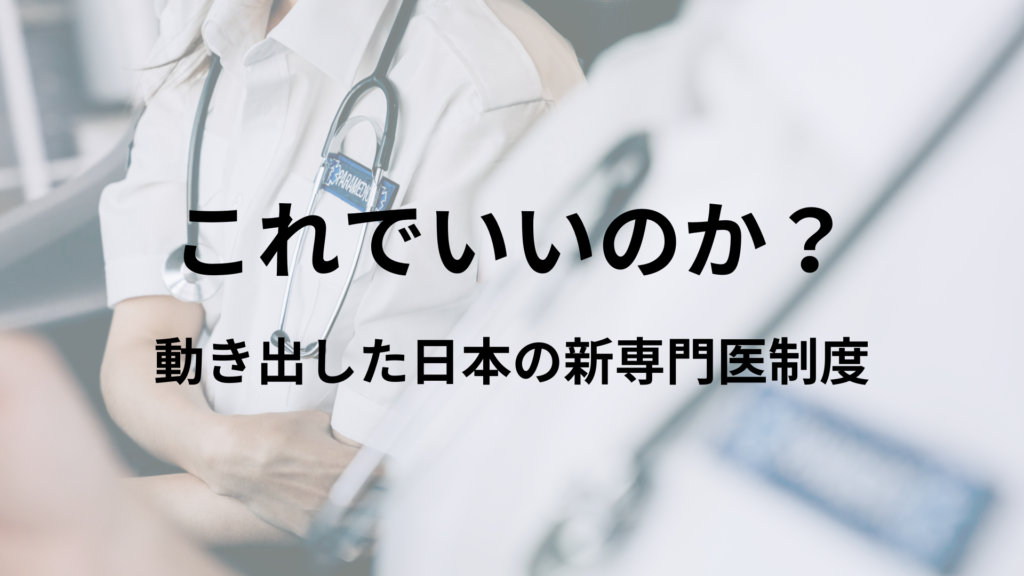
新専門医制度はなぜ導入された?いままでの専門医制度の問題と、新専門医制度のこれからの課題を解説します。
医師として活動するためには医師免許を取得しなければなりません。
そしてさらにそれぞれの専門科目に分かれて業務を行い、専門医の資格を取得する、というのが医師の基本的なキャリアとなっています。
この専門医制度、実は2018年に従来の専門医制度から新専門医制度に移行しているのです。
そもそも専門医というのはどのような団体がどのようにして認定しているものなのかよくわからないという人も多いかと思われます。
今回は2018年以前の専門医制度と新専門医制度の違いや新専門医制度のこれからの課題について解説をしていきます。
そもそも専門医とは
そもそも専門医というのはどのようなものなのでしょうか。
一言に「医師」といっても内科医か外科医かによって必要とされる技術や知識が大きく異なります。
さらに内科だけでも循環器内科、呼吸器内科、内分泌内科、血液内科・・・など、非常に多岐にわたる専門家があり、医師の業務というのは非常に細分化されています。
その細かく分かれた分野それぞれが異なる専門性を持っているのです。
医師免許を持っていると広大かつ高度に細分化された医師の業務をほぼ全てできるようになるのですが、それでは個人個人の意思が自ら標榜する科の知識や技術が十分にあるかどうかがわからなくなってしまいます。
そこで「細分化する医療の分野において高度な知識、技術、経験を持つ医師・歯科医師」
を専門医と定義して専門医を認定する必要があるのです。
従来の専門医制度とその問題点
まずは新専門医制度に移行する前の専門医制度はどのようなものであったのか見ていきましょう。
旧専門医制度において、専門医を認定していたのはそれぞれの領域の「学会」でした。
学会とはその領域の研究を目的とした医師の集団であり、日本内科学会、日本外科学会といったメジャーで多くの医師が在籍するような学会から日本温泉気候物理医学会というようなあまり聞きなれないような学会まで様々あります。
これら大小様々な学会が管轄する領域の専門医を独自に認定していました。
学会が認定する専門医も医師としての経験や知識、技術を証明するもので、その科の専門性を持っているかどうかの目安としては有効だと思われます。
しかし学会が独自に認定しているということから問題点も指摘されていました。
まず大小様々な学会が特に専門医制度を総括する組織なく各々の領域の専門医を認定しているため細かい領域の専門医が乱立されるような状況になっています。
「何その専門医資格?何ができるの?」と思わず聞きたくなるような専門医の資格がクリニックや医院の広告のために使われるなど、知識や技術の証明というより集客のための資格になっていた側面は否めないのです。
このようなカリキュラムを作る学会自体の乱立が起こりました。その数なんと100を超えます!
なぜ、こんな乱立が起きたのでしょうか?
専門医を取得するには、学会に「在籍年数」「学会や研修会への出席回数」などに応じて費用がかかります。
例えば、
● 「~学会」への在籍費用:年間1万円~2万円
● 学会への参加や発表:参加費用 1回 1万円~2万円
● 試験費用:1回 1万円~2万円
といったようにです。
しかも大体の学会は「更新制」になっているので、更新費用が別途かかります。
20年間「専門医」を名乗るのなら50万くらいお金がかかる計算になるでしょう
一言でいうと「利権の巣窟」になったのです。
また専門医を統括する公的な機関がないため、専門医を取るための要件に統一した基準がなく、それぞれの専門医の資格が真に実力を反映するものであると証明することが難しい状況でした。
そのため専門医資格を取得していることで給与や待遇に反映しにくいという問題があります。
専門医をとっているが特に仕事に変化を感じないという医師も多いのです。
これらの問題を解決するために2018年に新たな専門医制度ができたのです。
新専門医制度はどのようなものなのか
先述したように以前の専門医制度は統一した基準がなく乱立しがちであったことが問題でした。
そこで新専門医制度では統一的な基準を用いて専門医を認定することで、その質を担保する方針となっています。
新専門医制度では「日本専門医機構」が専門医制度を運営し、専門医の認定を行います。
この機構は学会に対して中立の第三者機関であり、各々の学会独自の基準であった従来の専門医制度から、日本専門医機構による統一的な専門医制度に変化したのです。
新専門医制度の問題点
従来の問題を解決すべく施行されている新専門医制度ですが、新たに課題が出てきているのも事実です。
まず新専門医制度で認定されるのは19の基本領域と29のサブスペシャリティ領域のみとなっています。
基本領域というのは内科や、外科、産婦人科といった基本の診療科の領域です。
この基本領域の専門医を取得したらその後より細分化した専門性の高いサブスペシャリティー領域の専門医を取得します。
例えば、内科で言えば血液、神経、糖尿病、呼吸器などがあります。
呼吸器内科の専門医を例にすると、まず基本領域の内科専門医を取得してそのあとサブスペシャリティの呼吸器内科の専門医を取得するという流れです。
ここでは日本の診療科別医師数と専門医数を表にまとめています。
地域によっては診療科の専門医がいないといったことを感じる方がいるかもしれません。そのため、新専門医制度では「シーリング」と呼ばれる専門医偏在化を改善する試みが実施されています。
| 診療科別医師数 | 専門医名称 | 専門医数 | ||
| 診療科名 | 従事する医師数(複数回答) | 主に従事する医師数 | ||
| 内科 | 88155名 | 61878名 | 総合内科専門医 | 14753名 |
| 外科 | 28918名 | 16704名 | 外科専門医 | 21816名 |
| 小児科 | 30344名 | 15870名 | 小児科専門医 | 14827名 |
| 産婦人科・産科・婦人科 | 13617名 | 12369名 | 産婦人科専門医 | 12227名 |
| 皮膚科 | 14892名 | 8470名 | 皮膚科専門医 | 5956名 |
| 精神科 | 15599名 | 14201名 | 精神科専門医 | 10099名 |
| 整形外科 | 24679名 | 19975名 | 整形外科専門医 | 17546名 |
| 眼科 | 13034名 | 12369名 | 眼科専門医 | 10594名 |
| 耳鼻咽喉科 | 9315名 | 9032名 | 耳鼻咽喉科専門医 | 8501名 |
| 脳神経外科 | 7385名 | 6695名 | 脳神経外科専門医 | 7111名 |
| 泌尿器科 | 8329名 | 6514名 | 泌尿器科専門医 | 6353名 |
| 救急科 | 3070名 | 2267名 | 救急科専門医 | 3382名 |
| 放射線科 | 9585名 | 5597名 | 放射線科専門医 | 5914名 |
| 麻酔科 | 10048名 | 7721名 | 麻酔科専門医 | 6345名 |
| 病理診断科 | 1615名 | 1515名 | 病理専門医 | 2188名 |
| 臨床検査科 | 735名 | 480名 | 臨床検査専門医 | 652名 |
| 形成外科 | 3319名 | 2135名 | 形成外科専門医 | 2102名 |
| リハビリテーション科 | 16604名 | 1909名 | リハビリテーション科専門医 | 1787名 |
従来の様々な学会が認定していた細かな専門領域の専門医資格はこの新専門医制度では認定されないのです。
そのため新専門医制度から漏れる内容の専門性を示す資格の取り扱いは曖昧になってしまいます。
また専門医を取得するために機関病院と連携病院を行き来しながら研修を行うことが定められましたが、この機関病院が地方には少ないのです。
専門医を取得する途中の医師が都市部に集中してしまい地域の医師が少なくなる、専門医取得を目指す医師が転勤を繰り返さないといけなくなるといった問題が出現しています。
まとめ
今回は新専門医制度について解説していきました。
新専門医制度への移行で専門医の認定の基準がある程度明確になり専門医の質の担保が図られる一方で専門医制度の縮小や医師偏在の助長など様々な問題が課題となっています。医師や患者にとってよりよい制度になるようにブラッシュアップされていくことが望まれます。
参考文献
3.横山彰仁.新・内科専門医制度について. 日内会誌 2015;104:2539-2546.
4.渡辺毅.新しい内科系専門医制度の概観―歴史的経緯を踏まえて.日内会誌 2015;104:1152-1159.
5.渡辺晋一.「日本と海外の専門医の違い」.日本医事新報社.
6.高宮有介.新専門医制度の現状と今後の課題.ファルマシア 2016;52:293-297.
7.池田康夫.新しい専門医制度. 厚生労働省へき地保健医療対策検討会 2015.



とは?-子ども時代の体験が-大人になったときの-心と体に影響-150x112.jpg)
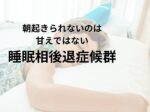


-150x112.png)

-150x112.png)

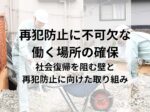






-300x169.jpg)