- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 裸眼視力1.0未満の中学生が61.23% テレビを見すぎると目が悪くなる?
-1024x576.png)
みなさんは子どもの頃、
「テレビから離れて見なさい!!」
「いったいいつまでテレビを見ているの?目が悪くなるでしょ!!」
と親から怒られたことはありませんか?
その時、子どもながらに思ったはずです。
「本当にテレビを近くで見たり、見すぎると目が悪くなるのだろうか?」
と、腑に落ちないような、理不尽に怒られた経験をしたことがある人もいるかと思います。
この昔からの言い伝えは、単なる迷信ではなく、現代科学によって裏付けられつつあります。
そして現在、テレビやスマートフォン、タブレットなど、様々な画面に囲まれた生活を送る子どもたちの視力低下が、深刻な問題となっています。
特に、学童期(およそ6歳~12歳)は視力の発達が重要な時期であり、適切な目のケアが必要です。
今回は、最新の研究をもとに、子どもの視力がどのように悪化しているのか、テレビ視聴と視力の関係、そして、親としてできる視力保護の方法について考えていきましょう。
どんどん悪くなる子どもの視力
実は、子どもの視力は深刻な状況になっています。
昔は、子どもで視力1.0以上は当たり前でしたが、今や視力1.0は「普通ではない」状況になっているのです。
文部科学省による「令和4年度学校保健統計調査」によると、各成長期における裸眼視力1.0未満の方の割合は、次の通りになっています。
| 2012年度 | 2022年度 | |
| 幼稚園 | 27.52% | 24.95% |
| 小学校 | 30.68% | 37.88% |
| 中学校 | 54.38% | 61.23% |
| 高等学校 | 64.47% | 71.56% |
ちなみに昭和60年度では、高校生で裸眼視力が1.0以下の割合が51.65%。
年を追うごとに「目が悪い子ども」が、どんどん増えていることがわかりますね。
特に、小学校からの視力の低下が著しい傾向にあります。
幼稚園では、平成24年度と令和4年度と比較しても、むしろ視力が低下している割合は減っていますが、小学校では、平成24年と比較すると、7%以上の増加になっています。
そして、その傾向は中学校、高等学校にも引き継がれ、それぞれ7%の増加となっています。
このように、子どもの視力は小学校を起点にして悪くなってきているのです。
(参照:文部科学省「学校保健統計調査-令和4年度(確定値)の結果の概要」)
子どもの視力が悪くなっている原因は?
では、どうして子どもの視力は小学校から悪くなってきているのでしょうか?
最新の研究から以下のことが言われています。
① 屋外活動が減ってきているから
② 近くで物を見る作業が増えてきているから
実は、近くの物を長時間見ることは、眼の屈折システムに負担をかけ、近視を促進する可能性があります。
ある研究によると、
- 30 cm 以下の距離で作業をする子どもは、それ以上の距離で作業をする子供に比べて、近視の割合が 2.5 倍になった。
- 1 回の読書時間が 30 分以上の子どもは、30 分未満の子どもよりも近視の発症率が高かった。
などの報告が上がっているのです。
| 要因 | 近視の割合 | |
| 1 | アジア人で あること | 11.0倍 (OR 11.0,p<0.0001) |
| 2 | 両親のうち 1人以上が近視 | 2.7倍 (OR 2.7,p<0.001) |
| 3 | 30cm以下の 近見作業 | 2.5倍 (OR 2.5,p<0.001) |
| 4 | 30分以上の 読書時間 | 1.5倍 (OR 1.5,P=0.02) |
③デジタルデバイスをよく利用するようになってきているから
スマートフォンなどのデジタルデバイスと近視の研究に関するLanca の報告では、15 件の研究のうち7つの研究で、スクリーンタイム(ゲームやスマホなどの使用時間)と近視の関連が認められています。
このように、近年、小学生から近視が進んできていることの背景として、さまざまな要素が絡んでいることがわかるでしょう。
(参照:京都女子大学生活福祉学科紀要 第17号 令和4年(2022 年)2月「小児期の近視の進行要因と予防」)
テレビと子どもの視力の関係は?
よく昔から「テレビを見すぎると目が悪くなる」といわれていますよね。
本当にそうなのでしょうか?
結論からいうと、日本の岡山大学で行われた大規模臨床試験で、「テレビの視聴時間と子どもの視力低下の関係性」が確認されています。
実際に論文の内容を確認していきましょう。
同論文は、「幼少期のテレビ視聴時間と、その後の小学生の視力低下を親が抱く懸念」について調査した論文です。
視力検査は、日本では3.5歳から行われ、学校健康法に基づき、小学校に入学してからも毎年実施されます。
これを利用して、幼少期のテレビ視聴が、どのように子どもの後期の視力に影響を与えるかを調べました。
対象者は、2001年に日本で生まれた、47,015人の生後6ヶ月から15歳までの子どもたち。
彼らに年齢に応じたアンケートを用いて、子どもたちのテレビ視聴習慣とその日々の視聴時間、親が子どもの視力低下に関して、どれくらい心配しているかを含めて調査しました。
結果、1.5歳と2.5歳の時にテレビを「主な娯楽」としていた子どもたちは、7歳から12歳の間に行われた6回の調査で、親が子どもの視力低下を心配する割合が高かったことが分かったのです。
2.5歳の時に、1日2時間以上テレビを視聴していた子どもたちは、小学校時代に視力低下に関する親の懸念が強くなる傾向がわかりました。
このように、子どもが小さいころにテレビを見ていると、成長したあとに親が視力に関して心配しやすいことがわかりました。
アンケート調査のため、子どもの視力低下との関連性は同論文では示されていませんが、ある程度テレビと視力低下に関連性があることは十分示されていると思います。
子どもの視力を守るために、親ができること
最後に、子どもの視力を守るために、親ができることを4つご紹介します。
①屋外活動を積極的にやってみる
子どもたちに、毎日の屋外での遊びやスポーツを奨励しましょう。前述の通り、自然光の下での活動は、視力保持に有効です。
家でテレビを見るより、積極的に外で思い切り遊びましょう。
②スクリーンタイムを管理する
ついつい、スマートフォンで遊ばせていると、子どももおとなしくなるので使ってしまいますよね。しかし、前述の通り、目にはタブレットやスマートフォン、テレビはあまりよくありません。
デジタルデバイスの使用時間を制限し、まずは、20-20-20のルール(20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る)を実践してみましょう。
➂適切な照明の確保してあげる
教育水準が高くなっている中、読書や勉強は必須ですし、目のためにそれらを制限するのは得策ではありません。
そこで気をつけていただきたいのは「照明」です。
子どもが読書や勉強をする際は、十分な照明を用意し、目への負担を減らしてあげましょう。
暗い場所での読書やスクリーンの見過ぎは、視力低下のリスクを高めます。
④定期的な視力検査をする
やはりどんな疾患でも、検査をしなければ発見することができません。
なかなか普段の子どもの生活を注意深く見ていても、子どもの視力は推し量ることができないもの。
「視力検査してはじめてわかった」という方も少なくありません。
そこで、定期的に眼科医の検査を受けさせましょう。
早期発見と対処してあげることで、視力低下を防げるほか、視力低下に伴う学力の低下や生活の障害を防ぐことができるでしょう。
子どもの視力の悪化は、放置していると一気に進みます。
確かに、日本の子どもたちの視力低下は、著しくなっています。また、ゲーム機やスマホのデジタルデバイスの登場や、SNSでの連絡の取り合い、外で活動する機会が減っている中、それは「仕方ないこと」かもしれません。
しかし、時代の流れで犠牲になるのは、私たちの「子どもたち」です。
そして、上記のように、親の私たちが子どもたちの視力を回復させるために出来ることは、いっぱいあります。
ついつい共働きで、自分たちの仕事で忙しかったり、テストや学力の向上などで子どもたちの健康に目が届きにくいのが、今の現代。
ぜひ、子どもたちの「目の健康」にも目を向けてみてください。
とは?-子ども時代の体験が-大人になったときの-心と体に影響-150x112.jpg)
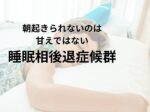



-150x112.png)








-280x210.png)

の看板-280x210.jpg)

-300x169.jpg)