- Home
- ライティングコンテスト
- 共存か?依存か?生成AIで得られる未来、失う未来
共存か?依存か?生成AIで得られる未来、失う未来
- 2024/2/26
- ライティングコンテスト
- 佳作, 第4回ライティングコンテスト
- コメントを書く
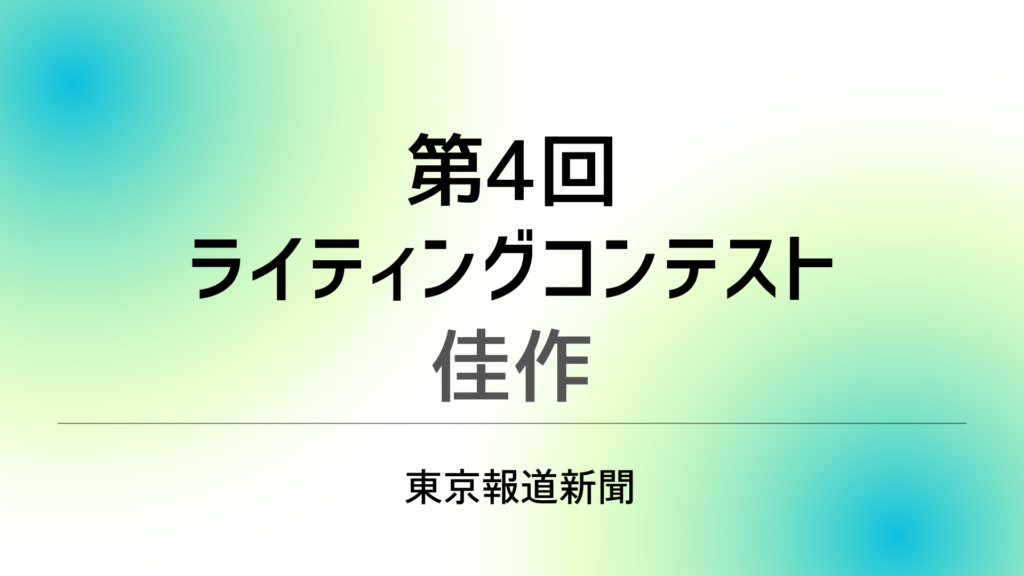
私たちの生活に静かに浸透してきた生成AI。気がつけば、今や日常の一部になりつつあります。
情報検索からクリエイティブな活動、さらには日常の決断まで。AIとの共存はもはや避けられない未来です。しかし、AIは利便性と効率性をもたらす一方で、私たちの生活や文化に深い影響を与え、新たな問題を示しています。
本稿では、この急速に進化し続ける生成AIが、私たちの未来にどのような影響を与えるのか、そしてどのように共存していけるのかを考察します。
AIの台頭により変わっていく日常
生成AIの台頭により、私たちの日常生活は大きな転換期に立たされているのを実感します。かつて時間を要していた情報検索は、AIの力で瞬時に結果を得られるようになりました。例えば、レシピ検索やニュースの要約、専門的な質問に対する回答など、日々の情報収集が劇的に効率化されています。
コミュニケーションの分野でも、AIは大きな変化をもたらしています。AIチャットボットは、カスタマーサポートから個人的な会話アシスタントまで、多様な形で私たちの対話をサポートします。言語の壁を超える翻訳機能は、世界中の人とのコミュニケーションを容易なものに変えました。
また、エンターテインメントの分野では、生成AIが映像や音楽コンテンツを作り上げ、その精度や品質は日々進化を続けています。すでに、AI作品によるビジネスやアイドル、タレントなどクリエイティブな楽しみ方が広がりを見せています。
これらの例は、AIが日常生活をどのように変えているかの一端に過ぎません。AI技術の発展により、これからもさらなる利便性と効率性の向上が期待されています。
AIへの依存で失われていくもの
AIの恩恵により、私たちの生活や仕事は便利になりました。しかし一方で、AIへの依存がもたらすリスクにも目を向ける必要があります。私が特に懸念しているのは、人や社会とのつながりが弱体化することです。AIによる即効性のある問題解決能力は、自ら考え探求するプロセスを軽視する傾向につながりかねません。
かつて私が少年時代だった頃、と言ってももう30年ほども前の話です。当時の問題解決方法と言えば、図書館や本屋に足を運び実際に本を手に取ったり、恩師や友人に相談したりするくらいの手段しかありませんでした。やがて、インターネット時代に突入。分からないことは「Google先生に聞く」時代です。情報がネット上に溢れ、答えを探すリサーチ能力が問われる時代でした。そして今は「ChatGPTに問題を丸投げ」し、答えがすぐに弾き出される時代になりました。そう考えると、私が少年時代に経験した問題解決方法は非効率でしかないでしょう。しかし、非効率が全て無駄な行為かと言われれば、決してそのようなことはありません。
確かに非効率な行動にはネガティブな一面があります。例えば、せっかく図書館に行ったのに目当ての答えが見つからない。恩師に相談したのに聞き入れてもらえない。はたまた、調べ物の途中で他の気になる情報に目が止まってしまい、目的から脱線してしまう。これは「非効率あるある」の現象です。
ですが、苦労したからこそ得られる喜びがあったのも事実です。恩師や友人との会話で得られた共感もありました。脱線したからこそ、新たな発見に出会ったこともあります。これらの経験は私自身の知的好奇心を高め、自分で考える力を形成したもののひとつであると確信しています。
答えを最速最短で出す生成AI。おそらく、問題の答えを求めるだけに関して言えば正解なのでしょう。しかし、悩みや葛藤、回り道をしない正解には危機感を感じずにはいられません。
学校の苦手な宿題と言えば読書感想文。この読書感想文を、ChatGPTで一瞬で作ってしまう、という問題が一時期話題になりました。私も小学生の頃は、イヤでイヤでしょうがなかった読書感想文の宿題。ですが、書き終わった後はなんとも言えない達成感を覚えたものです。後から読み返すとひどく稚拙な文章でひたすら後悔するのですが、これもひとつの成長のカタチと言えるでしょう。
AIの過度な依存は、人の創造性や批判的思考能力の低下につながります。自分自身で考え、アイデアを生み出す力は、AIには模倣できない人の重要な特性です。AIの利用は、これらの人らしい資質を補完するものであるべきで、置き換えるものではありません。
AIとのバランスを模索し続けることが共存の道
AI時代における重要な課題。それは、AIの恩恵を受けつつも、そのバランスを模索し続けることではないでしょうか。
私の本職はWebライターです。文章生成AIの発展により、仕事が無くなると言われたWebライター。ですが、実際には仕事が無くなることはありませんでした。むしろ、AIを多用することで業務が効率化され、今までよりも多くのマルチタスクをこなせるようになりました。
記事のアイデア出しから、構成の枠組み作り、そして執筆の下書きに至るまで。あらゆる業務にAIは利用できます。しかし、全ての工程で自己チェックをし、是正していかなければ使い物にはなりません。あくまでも、AIは自分の描く完成イメージをカタチにするまでの補助的な役割です。
2010年、スマホの普及率はおよそ4%ほどでした。それが、この10年ほどで誰もが1台は持つほど急速に普及し、私たちの生活に無くてはならないものになりました。そして、今はAI黎明期と言われる時代。AIとの共存が避けては通れない未来なら、私たちは少しでも多くAIに触れ、共存するためのバランスを常に考え続けなければいけません。
生成AIが無くてはならないパートナーになり、私たちの知的好奇心を色々なカタチに変えて実現していく未来。もう、すぐそこまで迫っています。
ライター:庭野ほたる
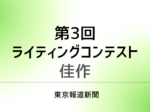
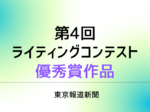
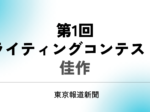

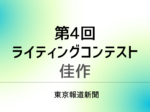

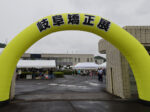


に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)
の看板-280x210.jpg)

-300x169.jpg)