- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 子どもの自己肯定感 自立に必要な能力を高めるには?
-1024x576.png)
自己肯定感とは、自分自身の価値を認識して自分を尊重する能力のを指します。
自己肯定感を育むことは心理的発達の基礎となり、自尊心、自身、自我を育てるための土台となります。
今回は、子どもの心理的発達を支えていく上でなくてはならない自己肯定感を、どのように育んでいくのかについて解説していきます。
なぜ今自己肯定感を育むことが重要なのか
人は成長していく上で勉強や仕事、スポーツや恋愛など、さまざまな課題に直面します。
自分の判断で行動をして、うまくいく時もあれば、大きな失敗をしてしまうこともあります。
そんな時に自己肯定感をしっかりと持っていると、自分の行動の良かったところを認識し、失敗した部分は次に同じ失敗をしないように、行動を変容することができます。
自己肯定感が低いと、自分の失敗ばかりに目がいき、行動を変える柔軟さが失われたり、そもそも失敗を恐れて行動することができず、仕事や恋愛などさまざまなチャンスを逃し続けてしまうことになります。
また、特にいま、自己肯定感が高い子どもを育てることに重要な理由があります。
それは、我が国の子どもたちの自己肯定感が低いというところにあります。
自己肯定感に関連する「今の自分が好きだ」という項目に、「はい」と答えた人は46.5%と、半数以上の人は自分を好きになれていないという結果が出ています。
そして、自己有用感に関して「自分は役に立たないと強く感じる」という項目で、「はい」と答える人が49.9%と、ほぼ半分となっています。
参照:内閣府. 令和3年度子ども・若者の状況及び子ども・若者育成支援施策の実施状況(令和4年版子供・若者白書)
そのほかの結果を見てみると、チャレンジ精神にかかわる質問「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」と答えた人は51.9%、社会貢献意欲の質問「社会のために役立つことをしたい」は70.8%となっていました。
この結果を見てみると、多くの人は社会に貢献したいと思っているにもかかわらず、低い自己肯定感と自己有用感のせいで、新しいことにチャレンジできなくなっているという状況が見えてきます。
これには日本の国民性が関わっていると思われます。
国民性調査第13次全国調査では、日本人の長所として「礼儀正しい」「親切」を選んだ人が過去最高となり、若年層で「煩わしさを避けて平穏無事に」と答える人が増えています。
このように、日本は他者との共生生活を乱さず、争いを好まない性質があり、そのため自己を主張して自己の肯定感を強めるというより、他者との関係性を重視しているのです。
参照:中村隆,土屋隆裕,前田忠彦.「国民性の研究 第13次全国調査−2013年全国調査−」 統計数理研究所 調査研究リポート 2015.No.116
つまり自己肯定感が低いことが、ただただ悪いことというわけではなく、日本人の協調性の裏返しで、日本という国の治安の良さや生きやすさに関わっている部分もあるのです。
しかし、そのなかでも自己肯定感を育むことができれば、他者と協調しつつ、新たな分野にチャレンジできる人材に慣れる可能性があり、我が国での自己肯定感を高める教育は、非常に有意義な物であることがわかります。
なにより、個人としての生きやすさに自己肯定感が関わっているので、自己肯定感を高めることで、子ども自身の生きやすさを高めることができます。
新たな分野へのチャレンジをできる子どもを育てることは、社会への大きな貢献となります。
自己肯定感を高めるために
まずは子どものことを認めるということです。
大袈裟に「すごいね」「えらいね」と褒めるというよりも、子どもが何かいいことをするたびに、ちゃんと「いいね」「いまのはよかったよ」と認めてあげることを意識してあげるのが効果的です。
これは、誰でもいつでも表現できるポジティブな行為で、無理がないので真意が伝わりやすく、相手への刺激も小さく褒めることに比べて飽きられることも少ないため、親子の関係構築や自己肯定感を育むことに最適なのです。
もちろん何か大きなことを達成したら、目一杯褒めることもとても良いことです。
次に、小さな成功体験をたくさん積ませることが重要です。
大きな目標を定めて、それを頑張らせようとすると、褒めたり認めたりする機会が減ってしまいます。
すぐに達成できる小さな目標をいくつも達成することが、自己肯定感には重要です。
まとめ
今回は、自己肯定感について解説をしていきました。
自己肯定感を高めることは、今後の我が国で活躍できる人になるための基礎となります。
自分は社会の中で役に立っているという実感をしっかり持ち、新たな分野で活躍できる人材となるように、自己肯定感を高める教育を実践していきましょう。
参考文献:



-150x112.png)



-150x112.png)





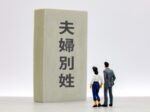

の看板-280x210.jpg)
に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)

-300x169.jpg)