
政府は2024年度に海底ケーブルの増設を進め、海外との新ルート開通や国内拠点の新設などを予定しています。これは、通信インフラの強化を目指す取り組みの一環です。政府はこうした民間事業を資金面から支援するとのことです。
「陸揚げ局」を含めた新たな拠点の創設は、災害や地政学リスクに強い分散型の通信網の形成を支えます。海底ケーブルはインターネットや国際電話に必要不可欠な基幹インフラで、日本の国際通信の99%を担っており、その役割は重大です。
今後10年で、回線需要は15~30倍になると予想されていることから、その需要に対応するための新ルート開拓が求められています。
政府は、総務省が2021年度に創設したデジタルインフラ整備基金の活用や、海外通信・放送・郵便事業支援機構などを通じた出資を考えており、その支援総額は数百億円単位にのぼる可能性があります。海外との新たなルートの候補としては日欧間が有力で、欧州連合(EU)は北極海を経由して日本と欧州をつなぐ「ファー・ノース・ファイバー事業」を支援しているとのことです。
また、日本の通信網につながる「陸揚げ局」の増設も進められており、北海道や九州での新設を含め、日本につながる支線も増やすことで通信の安定化を図ります。
なお、海底ケーブルの敷設工事は、米サブコム、仏アルカテル・サブマリン・ネットワークス、NECが市場を占有しています。彼らの活動に対してGoogleやMetaなどの直接投資も増えており、通信障害は安全保障に直結するため、海底ケーブルの増強が重要視されています。
海底ケーブルとは?全世界合計でおよそ地球30周分の長さ
2024年以降、政府によって莫大な資金が投じられる予定の海底ケーブルの増設。この海底ケーブルは、離れた地点を海底に敷設したケーブルでつなぎ、その通信網を通じて情報をやり取りする通信手段です。
海底ケーブルは耐久性を保つために独特な構造を持ちます。具体的には、通信線を中心に配置し、その外部を鉄線で覆うことにより、張力や海底との摩擦、海流による振動、錨(いかり)や漁具による損傷からケーブルを保護するというもの。
特に浅海部ではケーブルが損傷する危険性が高いため、ここではロボットによるケーブルの埋設が行われることもあります。その一方で、深海では状況が異なり、外部の鉄線による保護が必要ない場合もあるとのことです。
全世界の海底ケーブルをすべて足すと、その距離は約120万kmになるとのことで、これはおよそ地球30周分もの長さに相当します。とてつもない長さの海底ケーブルによって、世界がつながっていることが分かります。











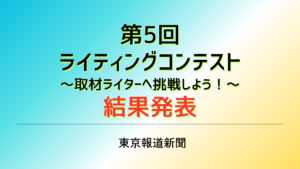
-300x169.png)


