- Home
- コラム・インタビュー, マネー・ライフ
- 「金融教育」生きるために子どもにこそ必要な教育
-1024x576.png)
「金融教育を小さなうちから実践している」
こういうことを言っている人を見かけたら、「珍しいな」「意識が高いな」「子どもにはまだ早いんじゃないか」というような感想を持つ方が多いのではないでしょうか。
そのような状況の中、我が国でも2018年3月改定の高等学校新学習指導要綱で金融教育についての動きがありました。
家庭科で資産形成に関する授業が、2022年の入学生から必須となっているのです。
高校で金融教育が行われることになったことについては、二つの要因が関係していると思われます。
一つは、成人の年齢が18歳からになることで、高校を卒業するとすぐに成人となり、資産形成などのスキルが必要になることです。
もう一つは、我が国の金融教育の遅れがあります。
実は残念ながら、諸外国と比較して日本の金融教育は、大きく遅れていると言わざるを得ない状況にあります。
そこで今回は、日本の資産教育の現状と資産教育を行うことのメリットについて解説をしていきます。
日本の金融教育は遅れている?
冒頭でも言及をしましたが、日本の金融教育、資産教育は諸外国と比べて明らかに遅れているのです。
日本の資産教育の現状をよく表している調査として、金融広報中央委員会が実施した「金融リテラシー調査2022年」の結果を見てみましょう。
学校などで金融教育を受けた人の割合は、日本では7%です。
アメリカは20%で、日本はアメリカの1/3程度の人しか金融教育を受けていないのです。
また、金融知識問題の正答率について諸外国と比較したところ、英国60%、ドイツ68%、フランス67%、日本59%と、日本が最も低いという結果になっています。
これらの調査を見てみると、日本はそもそも金融教育を受けている人、やっている場所が少なく、その結果、国民全体的に金融関係の知識が薄くなっているということがわかります。
| 日本 | 英国 | ドイツ | フランス | |
| 知識(正答率) | 59% | 60% | 68% | 67% |
| 行動 | 67% | 68% | 56% | – |
| 金融教育 | 行動特性・考え方 | → | 影響・結果 |
| 金融教育を受けている人が多め | 情報を頻繁に見ている家計管理がしっかりしている計画を立てている他の商品と比較している調査している相談している商品性を理解した上で購入緊急性の備えを持っている損失回避傾向が弱い | 金融トラブルが少なめ消費者ローンの利用が少なめ借り入れの負担が含め経済ショックへの耐性が強めリスク性資産への投資が多め |
日本の金融教育が遅れているのはなぜ?
日本の国民性として、「お金にこだわるのは汚い、醜い」と考える傾向があることが挙げられます。
このような国民性は、400年前の江戸時代から始まっています。
江戸時代、幕府が長期政権を築くために、さまざまな政策を行なっていました。
歴史の授業でも出てきた「士農工商」という言葉。これは身分を高い順に並べた言葉です。
商人が一番下の身分というのは、現在の価値観からすると違和感があります。
このような順番になった背景には、長期政権維持のために、お金に関する不満から国民が幕府を攻撃することのないように、国民がお金を欲しがらないようにするという目論見があったと考えられています。
また、日本人は家計の金融資産を現金や預貯金として保有する割合が高いため、金融資産の形成の仕方について、学ぶ機会が少ないというのも金融教育の遅れにつながっています。
日本銀行調査統計局による「資金循環の日米欧比較」によると、我が国の家計の金融資産構成は「現金・預金」が5割を超えています。
しかし、債務証券・投資信託・株式などの「金融商品」は15%にとどまっているのです。
同調査の米国の結果を見ると、「現金・預金」は14%で、「金融商品」は50%越えになっています。
このように、諸外国と比較して、日本人は投資商品に対して消極的であり、それにより積極的に投資や金融について学ぶ人が少ないのです。
子どもに金融教育を行うメリット
ここまで日本の金融教育が遅れているという話題ですが、「でも子どもにお金の話は早いのでは?」という方もいらっしゃるかもしれません。
ここからは、子どもがお金に向き合う必要性についてみていきましょう。
お金の問題は、大人になって直面するものと考えがちですが、子どもでもお金の問題に直面することは多くあります。
一つ例を挙げてみましょう。
スマートフォンが普及し、子どもがオンラインゲームなどに触れるようになり、親が知らない間に高額の課金をしてしまうという事案が増えています。
国民生活センターの発表では、小学生・中学生・高校生のオンラインゲームに関する課金トラブルは1,171件であったのが、2020年には3,723件となっています。
ボタンひとつで課金ができ、現金の受け渡しもないため、お金を使っているという感覚がないことも原因で、お金に対する認識がしっかりしていれば防げる事案です。
また、若年者が詐欺に遭う被害も増加傾向となっています。
消費者庁のホームページでは副業や内職、情報商材や転売ビジネス、投資用ソフトやビジネススクールといった、さまざまな儲け話に勧誘される「サイドビジネス商法」に関する消費生活相談件数が若者、全体共に増加傾向にあると注意喚起がされています。
その中でも、若者の相談が半数を占めており、20~24歳の相談件数が多くなっているとのことです。
マネーリテラシーがしっかりしていれば、詐欺であると気づいたり、違和感を感じて防ぐことができた事案がほとんどであると考えられ、子どもや若者の金融教育の重要性が浮き彫りになっているといえます。
金融広報中央委員会のホームページ「知るぽると」では、幼稚園から高等学校での金融教育の実践事集を公開しているので、金融教育とはどのようなことを行うのか確認し、子どもへの金融教育を考えてみましょう。
子どもへの金融教育の重要性
今回は金融教育について解説しました。
いまは諸外国に比べて金融教育が遅れている我が国ですが、今後は金融教育が進んでくることが考えられ、子どもに金融教育を行うことの重要性がますます高まってきます。
マネーリテラシーを高めることで、お金のトラブルなどを回避することもできますので、ぜひ金融教育を実践しましょう。
参考文献:
1.金融庁.金融広報中央委員会.「金融リテラシー調査2022年」
2.文部科学省.新学習指導要領について
3.日本銀行調査統計局.資金循環の日米欧比較
4.独立行政法人国民生活センター.オンラインゲーム
5.消費者庁. 簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
6.金融庁.金融広報中央委員会.金融教育の実践事例集



-150x112.png)


-150x112.png)



-150x112.png)
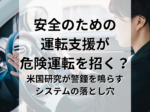






-300x169.jpg)