- Home
- コラム・インタビュー, 社会・政治
- 医師の行政処分 34年間で800人は基準が甘い?
-1024x576.png)
医師は人々を病気の脅威から守り、人の命を助ける大切な職業の一つ。
そのため、医師には非常に重い責任が伴います。
また、医師になるためには、特別な訓練が必要です。
そのため、高額な設備や学費が必要になってきます。
その影響があってか、医師は行政処分が甘いと言われ、以下のように様々な不満の声があげられています。
- こんな重大な過失で、ただの戒告処分なんて信じられない。
- 業界全体の信頼が失われる前に、何とかしないと。
- これでは若い医師たちがどんどんルールを破るようになる。
- 患者が被害を受けても、何も変わらないのか?
- こんな状況では、不正を告発する気にもなれない。
しかし実際、医師の行政処分の基準は本当に「甘い」のでしょうか?
また、医師が行政処分される時はどのような処分が下されるのでしょう?
今回は、具体的な金額や数字を用いて、医師の行政処分の実態について詳しく解説していきます。
医師の行政処分とは?
そもそも、医師の行政処分についてどこまで知っていますか?
行政処分を正確にいうと「法律に基づいて、行政が一方的に国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為」のこと。
本来は、誰であっても人間ひとりひとりの人生が最も尊重されるべきであり、何人たりとも人生を他人が左右するということはあってはいけません。
しかし、みんなが好き勝手やっていては社会として成り立ちませんよね?
そこで、国が間にはいって、「特別に悪質な行為」をした時に限って、「一方的に」様々な処分を下す権利を持っています。
これが「行政処分」です。
それは、人の命を救う医師だって例外ではありません。
「人の命を救うから」といっても、何でもやっていいというわけではないのです。
日本で医師が行政処分される基準については、医師法第7条に規定されており、以下の行為が「医師としての品位を損なう行為」として行政処分をうけます。
- 罰金以上の刑法にあてはまる行為:
医師が法に違反して罰金以上の罰を受けた場合です。例えば、大きな医療ミスをして患者さんに大きな損害を与えた場合などがこれに該当します。また、麻薬・大麻又はあへんの中毒者なども行政処分をうけます。 - 医事に関する犯罪や不正行為:
医師がお金をだまし取るような医療詐欺をした場合や、偽の薬を売った場合などがこれに当たります。 - 品位を損なう行為:
医師としてふさわしくない行動をした場合です。例えば、患者さんの個人情報を無断で公開したり、不適切な発言をした場合などがあります。 - 医療過誤・医療事故にあたる行為:
操作ミスや診断ミスなど、医師のミスによって患者さんに害を与えた場合も、行政処分の対象になります。 - 不正経営:
医療機関を運営している医師が、お金をだまし取るような不正な経営をしていた場合も問題です。 - 医療機器・医薬品の不正販売:
例えば、認可されていない医療機器や薬を売っていた場合も、行政処分される可能性があります。
ただし、これらの基準は今でも明確ではありません。
何が行政処分になるのかはケースバイケースであり、それぞれのケースによって個別に判断されます。
例えば、医療事故1つとっても、人間誰しも「ミス」をすることがあり得ます。
どんなに細心の注意をしたところで、万が一のことは起こりうる。
だからこそ、事前に十分説明して承諾をとってから医療行為を行うのです。
しかし、それでも医療事故が起こってしまったら、当事者としてはいたたまれない気持ちになり、医療者に怒りの矛先を向けるのは当然のこと。
そのため、第三者機関が十分検討して、「これは医療事故として行政処分をするべきなのか」を十分吟味される必要があるというわけですね。
では、実際、医師はどれくらいの確率で行政処分を受けるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
参照:日本医師会「医の倫理の基礎知識 2018年版【医師の基本的責務】A-9.医道審議会の組織と機能」
医師が行政処分される確率は?
まず結論からいうと「医師が行政処分される確率は高く、重くなってきたとはいえ、まだまだ低い」と言えます。
1971年から2004年3月までにおける医道審議会による行政処分について解析した結果によると、34年間に800人が行政処分をうけています。
そのうち、免許取り消し66人、医業停止734人となっており、医師585人、歯科医師218人という内訳です。
医業停止処分にされている対象は、以下の順に多く、
- 診療情報の不正請求
- 所得税法などの違反
- 医師法・歯科医師法違反
- 贈収賄
- 詐欺・窃盗罪
業務上過失致死が67人(うち医療事故51人)とのことでした。
令和2年12月31日現在における全国の届出「医師数」は339,623人。
そのうち、34年間に800人しか行政処分をうけていないので、行政処分されるまでのハードルはなかなか高いことがうかがえます。
では、医業停止はどれくらいの間、「停止」になるのでしょうか。
実は年代によって異なります。
1999年〜2002年は一律3か月、2003年は一律1年間、2004年は3か月〜3年6か月とかなり幅広くなっていますね。
おそらくこれは、2002年までは「医師には甘い行政処分」が、国民の目にさらされ「医師だけ不公平ではないか」という声が上がった結果、徐々に医業停止期間は長くなっていったと考えられます。
このように、徐々に医師への処分は重く、医業停止期間も長くなってきているものの、ほとんどの医師は行政処分を受けていないことがわかります。
参照:
医道審議会における医師・歯科医師の行政処分とその問題点~1971年から2004年までの34年間の統計的考察~
厚生労働省「医師」
医師の行政処分では、どのような処分が下される?
では、医師が非常に低い確率で行政処分が下されるとして、どのような処分が下されるのでしょうか。
具体的には「戒告」「医業停止」「免許取消」の3つがあげられます。
❶戒告
戒告は、医師が違法行為や不当行為をした場合に行われる最も軽い処分です。この処分では医師の業務に制限はかかりませんが、再教育研修が命じられることがあります。
この研修は、医師が再び同じ過ちを犯さないようにするためのものです。
❷医業停止
医業停止は、医師が一定期間、医業に携わることができないようにする処分です。停止期間は最長で3年です。この期間中に医業を行うと、法的に罰せられます。ただし、医業以外の業務(例:事務作業)は可能です。
❸免許取消
免許取消は最も重い処分で、医師の資格が完全に剥奪されます。ただし、一定の条件を満たせば、再免許の申請が可能です。この場合、最低5年から最長10年の待機期間が必要です。
各処分にはそれぞれ再教育研修が関連しており、研修を受けないとさらなるペナルティが科される可能性があります。
特に免許取消の場合、再免許を申請するには多くの条件と手続きが必要で、厚生労働大臣の裁量によって最終的な判断が下されます。
以上のように、医師の行政処分はその重さと影響が大きく異なります。
最も軽い「戒告」から、資格を失う「免許取消」まで、その範囲は広いものになります。
みなさんは、この医師の行政処分を「軽い」と思うでしょうか?「重い」と思うのでしょうか?
例えば、アメリカのニューヨーク州では独立した機関として「医療行為監視委員会(OPMC)」が事故調査権を任されています。
患者や遺族の委任または内部告発によって調査を開始し、症例の究明と過誤の有無を判定します。
結果、例年約30名に上る医師が、医師免許取消を相当とするとの判定を受けており、取消に至らないまでも、懲戒相当と判断された場合は、インターネット上に実名を公表しているのです。
それに比して日本では、2002年に昭和大学藤が丘病院で腹腔鏡による副腎の腫瘍摘出手術によって患者が死亡するという事故がありました。
医療ミスではないとした病院側の説明とは、別に泌尿器科学会関連の日本Endourology & ESWL学会は、2004年2月、昭和大学藤が丘病院で起きた腹腔鏡による医療事故の鑑定書を作成し、医療側のミスを明らかにしています。
また、ネットでは医療事故を犯した医師が何の処罰もなく医師として働いていることが容易にわかるでしょう。
ここでは参考までに士業の処分について表にまとめました。
| 処分権者 | 処分の種類 | 復権・ 免許再交付 | |
| 医師・ 歯科医師 | 厚生労働大臣 | 業務停止 免許取り消し | 明文規定なし |
| 弁護士 | 弁護士会 | 戒告 2年以内の業務停止 退会命令 除名 | 除名から 3年は不可 |
| 公認会計士 | 内閣総理大臣 | 戒告 2年以内の業務停止 登録抹消 | 除名から 5年は不可 |
| 税理士 | 財務大臣 | 戒告 1年以上の業務停止 業務禁止 | 業務禁止から 3年は不可 |
まずは「行政処分を受けない正しい医師」を育成することが大切
医師に対して行政処分が下されたということ。その先にはすでに「犠牲になってしまった患者さんとその家族」の存在があります。
しかし、重要なのは処分を受ける前に、どのようにして医師が正しい行動をとれるか、という点です。
医師が法的なルールや倫理規定をしっかりと理解し、それに従って行動することが何よりも大切です。
このような「行政処分を受けない正しい医師」を育成することが、医療業界全体の信頼性を高める鍵となります。
再教育研修や法的なペナルティは、あくまで問題が起きた後の対処法です。
それよりも前段階で、医師自身が持つべき倫理観や専門性を高める教育が必要なのではないでしょうか。
医師一人一人が自らの行動に責任を持ち、常に正しい医療を提供する意識を持つこと。
これが、最終的には医療業界全体の品質を向上させる最良の方法なのです。
昨今、医師の過労死の問題で話題になったように、今の医師が取り巻く環境は決して「最良」とは言えません。
よりよい改善が求められます。
参考文献:
1.根本晋一.医療事故に関する法律上の諸問題. 日本大学歯学部紀要 2006;34:85-95
2.医療安全推進者ネットワーク. 学会による鑑定書の作成で医療事故の原因解明へ
3.日経新聞 2004.03.18.昭和大学藤が丘病院泌尿器科における医療事故に関する外部事故調査委員会報告書



-150x112.png)









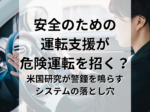




-300x169.jpg)