- Home
- コラム・インタビュー, 社会・政治
- 日本の子ども7人に1人が貧困 世界で25番目
-1024x576.png)
豊かな国というイメージがある我が国ですが、実は子どもの貧困が大きな社会的な問題になっています。
経済協力開発機構(OECD)が2015年に改定した新基準では、14.0%にまでなります。
実に、日本の子ども(17歳以下)の7人に1人が貧困状態ということになります。
実数に直すと、日本の17歳以下の人口は約1,890万人なので、約255万人です。
これは世界で比較すると、25番目の高さです。
そうです。
日本でも多くの子どもが、経済的に困窮した状況で生活しているのです。
日本の子どもの貧困の現状
子どもの貧困というと、発展途上国の問題などを想起する人が多いと思いますが、発展途上国における貧困というのは、国全体が貧困状態になって起こる問題で、日本の子どもの貧困とは少し事情が違います。
日本の子どもの貧困問題は「相対的貧困」と言われる状態です。
相対的貧困というのは、ある国やある社会といった人間の集団の中で、多くの人たちが享受できている生活水準を送れない状態を指します。
途上国のように、水もない、電気もないという状態とは違っても、その国の中で普通に行われてることが、貧困によりできないため、社会の中で大きく出遅れることになります。
つまり、相対的貧困というのは、社会の中の格差が生み出した貧困ということになります。
「相対的貧困」とは所得を世帯人数に振り分け、数値を出して、高さ順に並べたときに、その中央値の半分に満たない状況を言います。
つまり、その社会の中で、一番たくさんいる所得帯の人の半分の所得(貧困線)での生活をしている人ということになります。
「子どもの貧困」とは、貧困線に満たない子どもを指します。
日本での相対的貧困の目安は、親子2人が毎月14万円以下で暮らしている状況です。
日本では、ひとり親家族の相対的貧困率の高さが問題となっており、実に48.1%であり、これは2世帯に1世帯が相対的貧困にあるということになります。
ここでは、貧困に関するデータおよび、大学、専修学校への進学率についてそれぞれ表にまとめました。
| 調査対象年 | 相対的貧困率 | 子どもの貧困率 |
| 1997年 | 14.60% | 13.40% |
| 2000年 | 15.30% | 14.50% |
| 2003年 | 14.90% | 13.70% |
| 2006年 | 15.70% | 14.20% |
| 2009年 | 16.00% | 15.70% |
| 2012年 | 16.10% | 16.30% |
| 2015年 | 15.60% | 13.90% |
注)2013年「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
| 全世帯 | ひとり親世帯 | |
| 2003年 | 70.10% | 43.20% |
| 2006年 | 71.80% | 45.40% |
| 2011年 | 73.50% | 41.60% |
| 2016年 | 73.20% | 58.50% |
なぜ相対的貧困は良くないのか
「そうはいっても、なんとか衣食住は揃っているのだから、そこから頑張って這い上がればいい」という考えの人もいらっしゃるかもしれません。
貧しいところから這い上がった人の話などを見聞きすると、その様な考えが出ることもおかしなことではありませんが、ぜひ立ち止まって考えていただきたいことがあります。
相対的貧困にある子どもたちは、
「家計を支えるために毎日アルバイトをしている」
「高校、大学や専門学校等への進学を経済的理由からあきらめざるを得ない」
「1日で栄養のある食事を学校給食でしか摂取できていない」
といった状況が考えられます。
これが「貧困の遺伝」です。
もちろん、貧困になる遺伝子が見つかっている、という生物学的な話ではなく、貧困状態の家庭に生まれ育った人は、生まれながらの周囲の環境等から、貧困から抜け出せない可能性が高いのです。
例えば、教育について。高度な教育を子どもに受けさせようとすると、当然学費がかかります。
十分な所得のある家庭では、学校の他に塾に通ったり、苦手な分野があればそれをわかりやすく解説した教材を使ったり、様々な方法で学力を伸ばすことができます。
ところが、相対的貧困の家庭の多くは、高校の進学もままならないのです。
いくら才能を持って生まれて、勉学に励む素養があっても、高校に行けるかもわからず、大学は多額の借金をしないといけないことが確定してる様な状況で、ましてや塾なんかとんでもない、と言われて、平均より上の学力を、ましてや高学歴を目指すことは現実的ではありません。
そればかりか、子どもたちは周囲の家庭環境との差を目の当たりにして、自己評価や自尊感情が損なわれ、将来への希望がなくなり、学習意欲を失っている場合も多いと報告されています。
低学歴や貧困から這い上がるごく一部の例を見て、「貧乏でも学力は関係ない」と言ってしまうことは、才能を開花させる可能性があるのに、十分な支援を受けられない子どもを増やし、将来の貧困率を上げてしまう行為なのです。
学力がダメならスポーツはどうでしょうか。
ここでも当然貧困の壁は立ちはだかります。
Love.futbol Japanと言うNPO法人が行った調査では、支援世帯の実に約30%の子どもが、サッカーをするために「借入」をしていたという事実が判明しています。
つまり、経済格差のために、「良い環境でサッカーをする」というのではなく、「サッカーをする」ということができず、借入が必要という世帯が日本中に存在するのです。
健康面でも、貧困問題はついて回ります。
貧困家庭の子どもは、朝食の欠食率が高いことが知られており、成長期の身体形成、体力増進が阻害されたり、集中力の低下による学力へ影響が懸念されています。
また、医療機関への受診を控える、任意予防接種を控えるといった医療アクセスの問題が起きるのです。
貧困家庭であるほど、受動喫煙率が高いという報告もあり、貧困が両親の健康に対するリテラシーに直結する問題であることがわかります。
また、無視できないのが虐待リスクです。
世帯収入が低い家庭ほど、未就学児の虐待の割合が高いことが知られているのです。
また、子供の頃に貧困だった人は、成人になってからの虚血性心疾患、脳卒中、肺がんなどによる死亡率が優位に高いことも報告されています。
子どもの頃に、基本的な生活習慣や食習慣を確立できないことが原因と考えられています。
この様に貧困の世帯に育つと、貧困に起因する多くの問題が立ちはだかり、容易に這い上がれないのです。
そうして貧困家庭が減らず、経済格差の広がりで貧困状態に陥る人が増えると、ますます貧困から這い上がれない人が増えていくという、負のスパイラルに陥ります。
ついには、社会全体の機能が低下していくことにつながりかねません。
貧困問題は、貧困に喘ぐ当事者だけの問題でなく、社会全体で対処すべきものなのです。
まとめ
貧乏から努力で這い上がる。そのような話が美談とされていますが、努力でどうにもならない環境に置かれている子どもたちがたくさんいます。
確かに、裕福な家庭で育った方も、たゆまぬ努力の上で裕福さを保っているのは事実です。
しかし、豊かに見える日本社会でも、どう努力しても這い上がることが難しい状態に置かれている子ども達が、大勢存在します。
また、裕福な人も社会の変化のなかで貧困に陥ると、そこから抜け出すことが非常に困難な状況になっています。
貧困問題が社会全体の問題として捉えられ、多くの人が努力すれば自分の存在意義を見出せる、そんな未来が来ることを願って止みません。
参考文献:
1.Lia C H Fernald,Paul J Gertler, Lynnette M Neufeld. Role of cash in conditional cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico’s Oportunidades. Lancet . 2008 Mar 8;371(9615):828-37. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60382-7
2.公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
3.廣瀬伸一.子どもの貧困.日本医事新報社 2019;4941:101
4.Kyowa Kirin.日本でも子どもの7人に1人が貧困…「相対的貧困」の課題とは?.MIRAI REPORT
5.文部科学省.学校基本調査
6.Love.futbol Japan.「世界中にいるサッカーしたくてもできない子どもの「環境」を変える」
7.経済協力開発機構(OECD).貧困率
8.内閣府.子どもの貧困



-150x112.png)








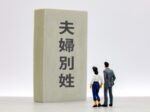


の看板-280x210.jpg)
に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)

-300x169.jpg)